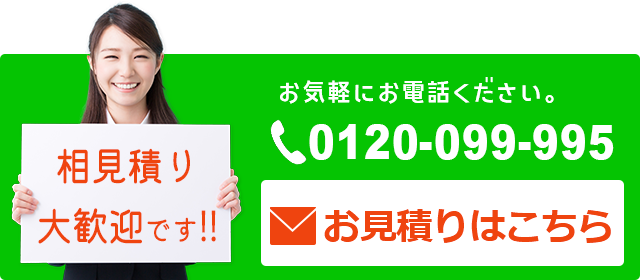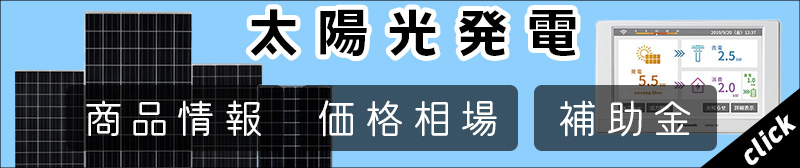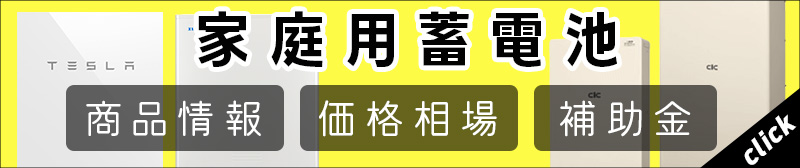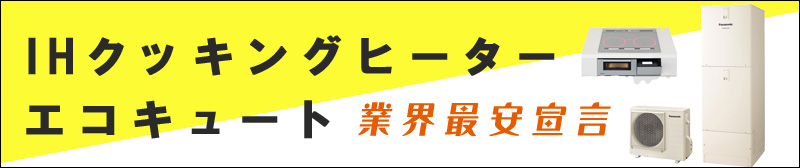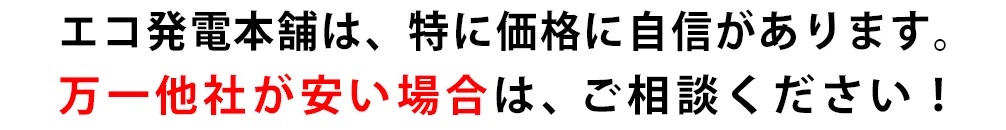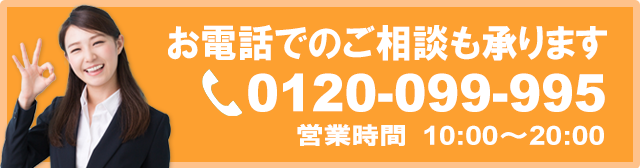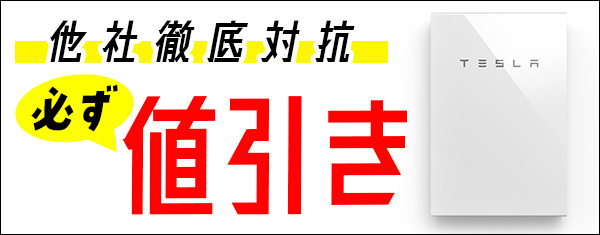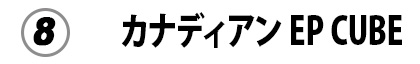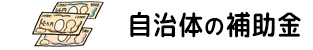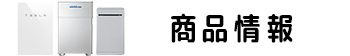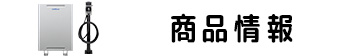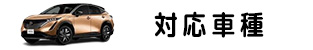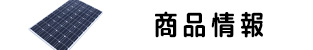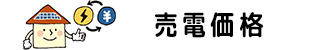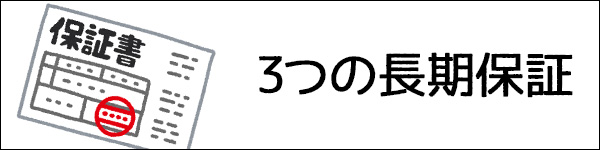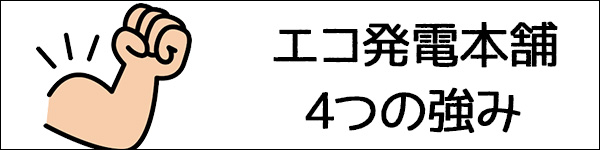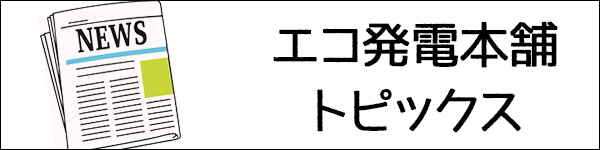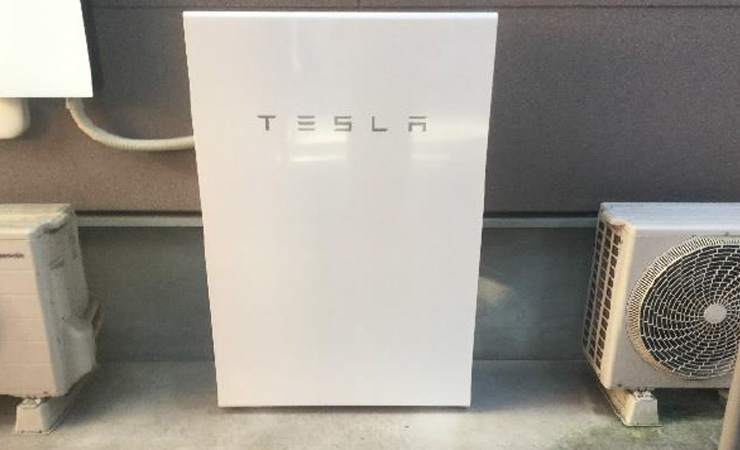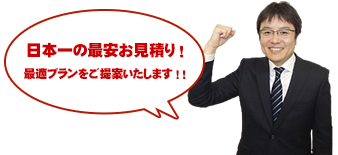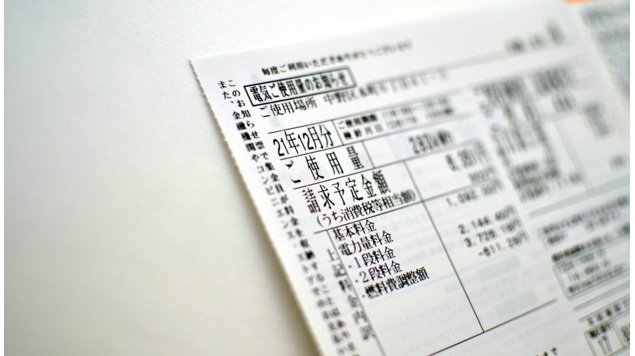
電気料金は複数の要素で確定している
最近、電気料金の値上がりが大きな話題になっています。2022年以降、燃料価格の高騰や円安の影響で、日本国内の電気料金は大幅に上昇しましとた。特に2023年には、多くの大手電力会社が家庭向けの電気料金を値上げし、家計への負担が増えています。
例えば、東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」プランでは、2022年と比べて2023年6月の電気料金単価が約20%上昇しました。
このように、電気料金は社会情勢の影響を受けやすく、知らないうちに支払う金額が増えている可能性があります。毎月の請求額を見て、「こんなに高かった?」と驚いたことがある方も多いのではないでしょうか。
電気料金は、ほとんどの家庭で毎月自動引き落としになっています。そのため、特に意識せずに支払っている方が多いのが現状です。しかし、その内訳をしっかり理解すると、意外な発見があります。
たとえば、電気料金の中には、実際に使った電気代(電力量料金)だけでなく、「基本料金」や「再生可能エネルギー発電促進賦課金」などの固定費や追加費用が含まれています。これらの費用は、契約内容によって変わるため、見直しによって電気代を抑えられることもあります。
本記事では、電気料金の内訳をわかりやすく解説します。
• 基本料金とは何か?
• 電力量料金の計算方法は?
• 再生可能エネルギー発電促進賦課金や燃料費調整額とは?
これらを順番に説明していきますので、最後まで読んでいただければ、毎月の電気料金の仕組みをしっかり理解できるはずです。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
電気料金の基本構造
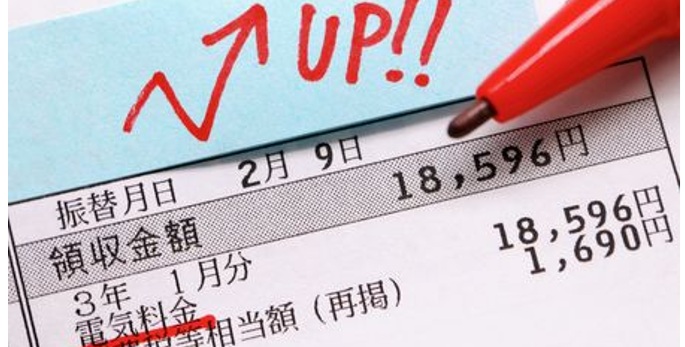
電気料金は大きく3つの要素で決まる
電気料金は、主に次の3つの要素で構成されています。
1. 基本料金(固定費):契約した電気の容量(アンペア)に応じて毎月発生
2. 電力量料金(変動費):実際に使用した電力量(kWh)に応じて決まる
3. 各種賦課金・調整額:再生可能エネルギー発電促進賦課金や燃料費調整額など、社会情勢に応じて変動
これらの合計が、私たちが毎月支払う電気料金となります。
たとえば、東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」プラン(2024年2月時点)を例にすると、次のような計算式になります。
電気料金=基本料金+(電力量料金単価×使用量)+燃料費調整額+再エネ賦課金
具体的に計算してみましょう。
(例)一般的な家庭(30A契約、月300kWh使用)の場合
• 基本料金(30A):858円
• 電力量料金
• 120kWhまで:19.88円×120kWh=2,385.6円
• 121〜300kWh:26.48円×180kWh=4,766.4円
• 燃料費調整額(※2024年2月時点の例):-3.00円×300kWh=-900円(燃料費調整がマイナスの場合、割引となる)
• 再エネ賦課金(3.49円/kWh):3.49円×300kWh=1,047円
合計:858円+2,385.6円+4,766.4円−900円+1,047円=8,157円
このように、電気料金は固定費と変動費、そして追加の調整額で成り立っています。
電気料金の決まり方
①電力会社ごとに料金プランが異なる
2016年の電力自由化以降、消費者は大手電力会社(東京電力・関西電力など)以外にも、新電力会社(楽天でんき、エルピオでんきなど)を選ぶことができるようになりました。
それに伴い、電力会社ごとにさまざまな料金プランが登場し、基本料金ゼロのプランや、特定の時間帯に安くなるプランなど、選択肢が広がっています。
②電気使用量が多いほど、単価が上がる「段階制料金」
多くの電力会社では、電力量料金に「段階制料金」を採用しています。これは、使用量が増えるほど単価が高くなる仕組みです。
東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」では、次のように設定されています(2024年2月時点)。
| 使用量(kWh) | 料金単価(円/kWh) |
|---|---|
| 120kWh以下 | 19.88円 |
| 121〜300kWh | 26.48円 |
| 301kWh以上 | 30.57円 |
つまり、電気をたくさん使う家庭ほど、料金単価が上がり、総額も高くなります。これを踏まえて、使用量が増えないように工夫することが節約のポイントとなります。
③政府や電力会社の政策によって変動する部分もある
• 燃料費調整額は、火力発電の燃料価格によって毎月変わるため、社会情勢によって大きく上下します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日本政府の政策によって年々上昇傾向にあります。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
電気料金の基本料金とは?

基本料金の仕組み
電気料金の中で、電気を使っていなくても毎月必ず発生するのが「基本料金」です。これは、電力会社が安定して電気を供給するための設備維持費などに充てられています。
基本料金は、契約しているアンペア(A)の大きさによって決まります。アンペアとは、一度に使用できる電気の容量のことで、家庭のブレーカーの設定によって変わります。
たとえば、30A契約の家庭なら「30Aまで同時に電気を使える」状態になっており、より多くの電化製品を同時に使うには、より大きなアンペア契約が必要になります。
アンペア別の基本料金一覧
東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」プラン(2024年2月時点)を例に、契約アンペアごとの基本料金を見てみましょう。
以下のように、契約アンペアが大きいほど基本料金も高くなります。
| 契約アンペア(A) | 基本料金(円/月) |
|---|---|
| 10A | 286円 |
| 15A | 429円 |
| 20A | 572円 |
| 30A | 858円 |
| 40A | 1,144円 |
| 50A | 1,430円 |
| 60A | 1,716円 |
自分の契約アンペアの確認方法
現在の契約アンペアは、以下の方法で確認できます。
1. 電気料金の明細を確認する:
• 「契約容量」や「契約A(アンペア)」の欄に記載されていることが多いです。
2. ブレーカーを確認する:
• 分電盤のブレーカーに「30A」や「40A」と記載されている数字が契約アンペアです。
3. 電力会社に問い合わせる:
• わからない場合は、契約している電力会社に確認すれば教えてもらえます。一番確実なので、自信のない方は問い合わせましょう。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
電気料金の電力量料金とは?

電力量料金の仕組み
電力量料金とは、実際に使用した電気の量(kWh)に応じて発生する料金です。基本料金と違い、電気を使った分だけ支払う「変動費」となります。
電力量料金は以下の計算式で求められます。
電力量料金=使用量(kWh)×料金単価(円/kWh)
料金単価は電力会社や契約プランによって異なりますが、多くの電力会社では「段階制料金」を採用しています。これは、使用量が増えるほど1kWhあたりの単価が上がる仕組みです。
段階制料金の仕組み
多くの電力会社では、使用量に応じて料金単価が変わる「段階制料金」を採用しています。東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」プラン(2024年2月時点)を例にすると、以下のような設定になっています。
| 使用量(kWh) | 料金単価(円/kWh) |
|---|---|
| 120kWh以下 | 19.88円 |
| 121〜300kWh | 26.48円 |
| 301kWh以上 | 30.57円 |
たとえば、1か月で300kWhを使った場合の電力量料金を計算してみましょう。
• 120kWh×19.88円=2,385.6円
• (300kWh−120kWh)×26.48円=4,766.4円
合計すると、電力量料金は7,152円となります。
電力量料金の計算例
①1人暮らし(使用量150kWh)の場合
• 120kWh×19.88円=2,385.6円
• (150kWh−120kWh)×26.48円=794.4円
• 合計:3,180円
②4人家族(使用量400kWh)の場合
• 120kWh×19.88円=2,385.6円
• 180kWh×26.48円=4,766.4円
• (400kWh−300kWh)×30.57円=3,057円
• 合計:10,209円
このように、使用量が増えると、段階制料金の影響で1kWhあたりの単価も上がり、総額が高くなります。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金
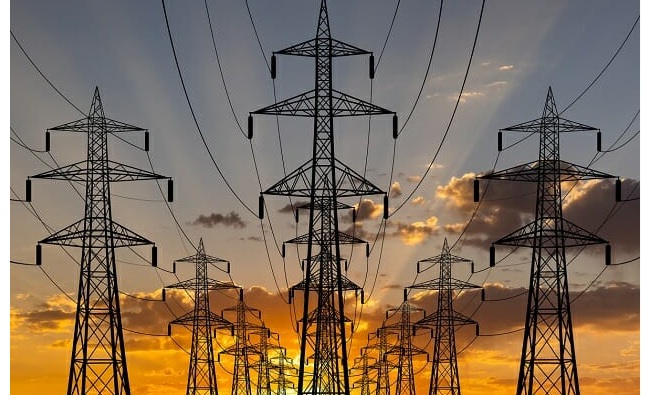
電気料金には、「基本料金」や「電力量料金」のほかに、毎月の料金が変動する「燃料費調整額」や「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」が含まれています。これらの費用は、社会情勢や政府の方針によって変わるため、電気料金の変動要因として重要なポイントになります。
燃料費調整額とは?
①燃料費調整額の仕組み
燃料費調整額とは、電気を作るための燃料(石炭・LNG(液化天然ガス)・石油など)の価格変動を電気料金に反映させる制度です。発電に使う燃料は輸入に依存しているため、国際的な原油価格や為替レートの影響を大きく受けます。
燃料費が高騰すれば電気料金も上がり、逆に燃料費が下がれば電気料金も安くなる仕組みです。
②燃料費調整額の計算方法
燃料費調整額は、3~5か月前の燃料価格の平均を基に計算されます。たとえば、2024年2月の燃料費調整額は、2023年10〜12月の燃料価格を基に決められます。
このように、燃料価格の変動に応じて、毎月の電気料金に影響を与えます。
③燃料費調整額の影響例
たとえば、1か月に300kWhの電気を使う家庭の場合、燃料費調整額が変わると以下のようになります。
• 燃料費調整額が+3.00円/kWhの場合→300kWh×3.00円=+900円
• 燃料費調整額が-3.00円/kWhの場合→300kWh×(-3.00円)=-900円(割引)
このように、燃料費調整額がプラスになると電気料金が上がり、マイナスになると料金が安くなります。
④燃料費調整額の今後の動向
• 2022年〜2023年にかけて、ロシア・ウクライナ情勢の影響でLNG価格が急騰し、燃料費調整額が大幅にプラスとなりました。
• しかし、2023年後半からは燃料価格が落ち着き、2024年2月時点では燃料費調整額がマイナスに転じています。
今後の動向は、原油市場や為替相場の影響を受けるため、定期的にチェックすることが重要です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)とは?
①再エネ賦課金の仕組み
再エネ賦課金とは、太陽光・風力・バイオマスなどの再生可能エネルギーの普及を促進するために、すべての電力利用者が負担する費用です。2012年に「固定価格買取制度(FIT制度)」が始まり、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定価格で買い取る仕組みが導入されました。
この買取費用を補うために、家庭や企業の電気料金に「再エネ賦課金」として上乗せされる形で負担されています。
②再エネ賦課金の推移
再エネ賦課金は年々上昇しており、以下のように増加しています。
| 年度 | 再エネ賦課金(円/kWh) |
|---|---|
| 2012年度 | 0.22円 |
| 2015年度 | 1.58円 |
| 2020年度 | 2.98円 |
| 2023年度 | 3.45円 |
| 2024年度 | 3.49円 |
1kWhあたりの単価はわずかですが、使用量が多い家庭ほど負担額が増えるため、無視できない費用になっています。
③再エネ賦課金の影響例
• 1か月に300kWh使用する家庭
300kWh×3.49円=1,047円(2024年度の場合)
• 1年間の負担額
1,047円×12か月=12,564円
つまり、年間1万円以上の負担が発生する計算になります。
④再エネ賦課金は今後どうなる?
• 日本政府は、2030年までに再生可能エネルギーの比率を高める方針を掲げています。
• FIT制度の見直しや、新たな再エネ支援策の導入により、再エネ賦課金の上昇ペースが緩やかになる可能性もありますが、今後も一定の負担は続く見込みです。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
電気料金のまとめ

これまで、電気料金の構成要素について詳しく解説してきました。最後に、電気料金の仕組みをも一度まとめます。
電気料金は、以下の3つの要素で構成されています。
1. 基本料金(固定費)
• 契約アンペア(A)によって決まる固定料金。
• 契約アンペアを下げると節約可能だが、適切な容量を選定。
2. 電力量料金(変動費)
• 使用した電力量(kWh)に応じて発生する料金。
• 段階制料金が適用され、使用量が増えるほど1kWhあたりの単価も上がる。
• 待機電力の削減、省エネ家電の活用、時間帯別プランの利用などで節約可能。
3. 各種賦課金・調整額(変動費)
• 燃料費調整額:燃料価格や為替レートに応じて毎月変動。
• 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金):再生可能エネルギーの普及を支えるための負担金。
• 燃料費調整額がプラスになると電気代が上がり、マイナスになると安くなる。
• 再エネ賦課金は年々上昇傾向にあり、今後も増加の可能性がある。
電気料金の内訳を知ることで、以下のようなメリットを得られます。
①電気料金の見直しのきっかけになり、家計の負担を減らせる
• 電気代の削減は、長期的に見ると大きな節約につながる。
• 例えば、月3,000円の節約ができれば、年間36,000円の節約に!
②将来の電気料金の変動に備えられる
• 燃料費調整額や再エネ賦課金の動向を知ることで、電気料金の変動に対応しやすくなる。
• 例えば、燃料費調整額が大幅に上昇する兆しがあれば、契約プランの見直しや省エネ対策を早めに行うことができる。
③自分に合った電力会社・プランを選べる
• 2016年の電力自由化以降、多くの新電力会社が参入し、選択肢が増えた。
• 料金プランの比較ができるようになり、自分に最適な契約を選べる。
電気料金の仕組みを理解していただくと、現在の電気料金がなぜこの価格なのかがわかってくると思います。適切な電力会社の使用や、電力プランの選定をする一つの材料になると思います。