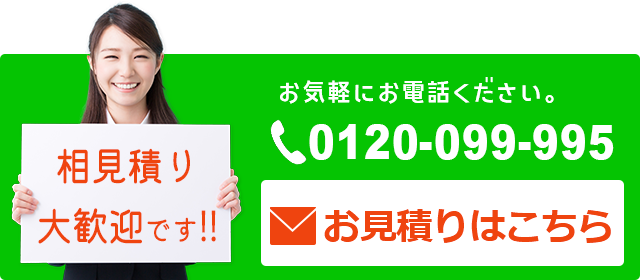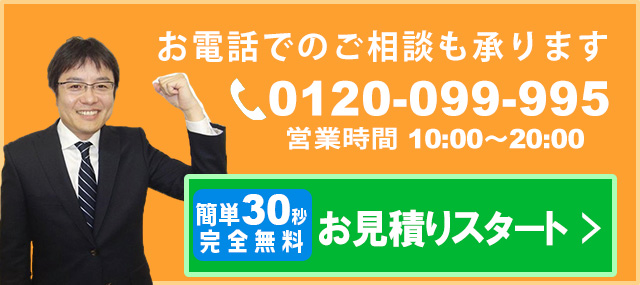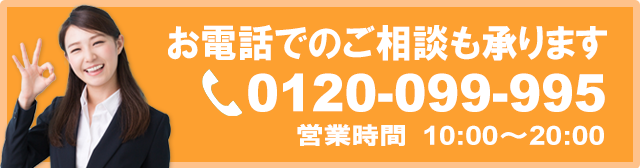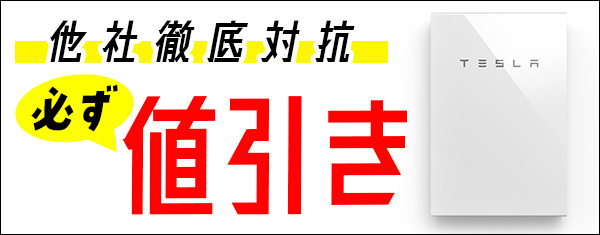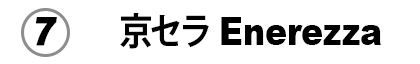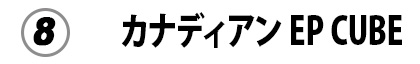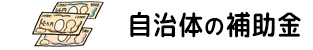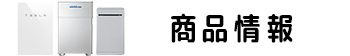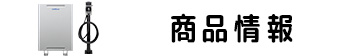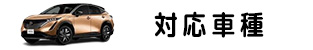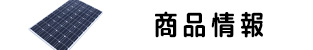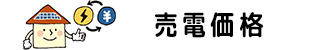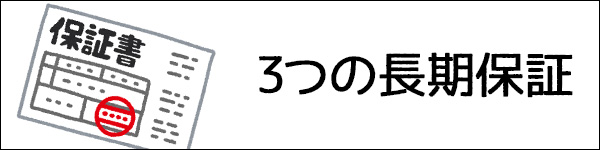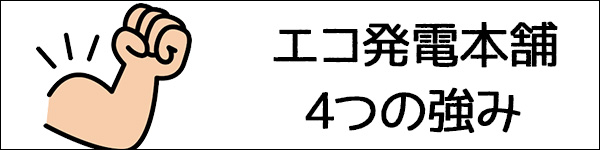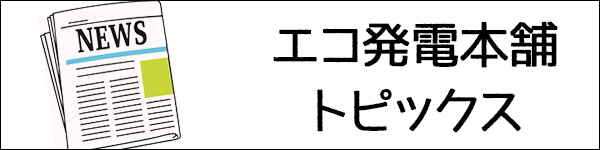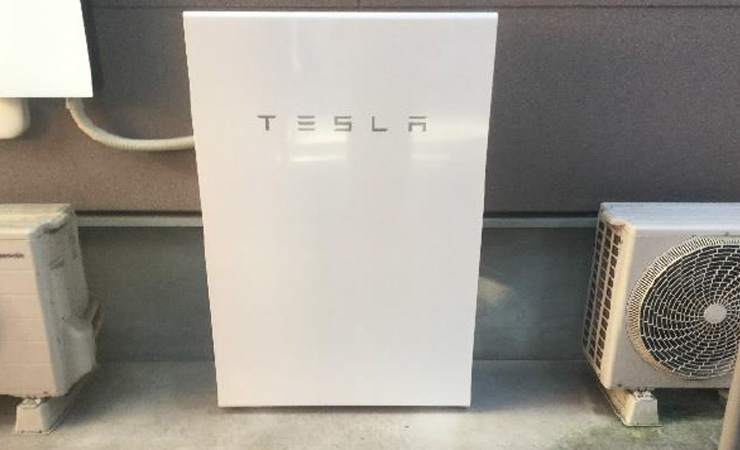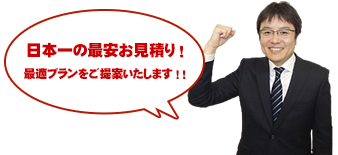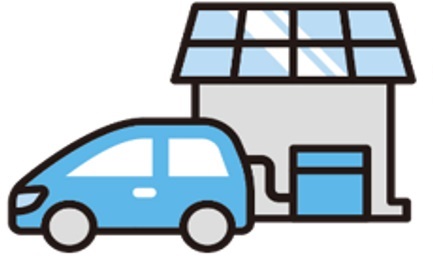
電気自動車や効率的なエネルギー利用を考えている人なら、H2Vに関心が高い人も多いのではないでしょうか。H2Vシステムがあれば、電気自動車のバッテリーも家庭用電源として利用することができます。停電や災害などが起こった際の予備電源としての備えになりますし、電気料金の節約も可能です。今回は、H2Vを導入することで便利になるポイントや導入の際に押さえておきたい注意点などを解説していきます。
V2Hの基本動作・商品比較はこちら
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hシステムの基礎知識
V2Hとは「Vehicle to Home」を略した言葉です。日本語にすると「車から家へ」という意味になります。Vehicleとは、本来乗り物全般を指す単語ですが、家庭に電力を供給する一般的な乗り物といえば電気自動車です。そのため、V2Hの場合は車と表現するほうがわかりやすいでしょう。
電気自動車のバッテリーには、電気が蓄えられています。V2Hは、その電気を家庭で有効活用する技術と考え方のことです。せっかくバッテリーに電気を蓄えても、車として乗らないときは無駄になってしまいます。蓄電力が大きい電気自動車のバッテリーを活用すれば、災害時の非常用電源としても便利です。ここでは、V2Hの基本的な仕組みや蓄電池との違いなどについて解説していきます。
一般的に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)などの電動車両は、大容量のバッテリーを搭載しています。V2Hは、こういった車両のバッテリーを活用して家庭や建物への電力供給やバックアップ電源として活用する技術やシステムのことです。通常、V2Hシステムでは車両と家庭の間に専用の充電器が設置されます。仮に、車両が充電された状態で家庭へと戻った場合は、「車両のバッテリーの電力を逆に流すことで家庭の電力需要を補える」というわけです。これにより、停電時や電力需要が増加した場合など、家庭での電力供給が一時的に保証されます。V2Hは、持続可能なエネルギーの普及やスマートグリッドとも関連した概念です。将来的には、V2H技術の進展によって車両や建物などのエネルギーシステムが統合され、より効率的なエネルギー管理が実現されると考えられています。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの基本的な仕組み
電気自動車があっても、バッテリーに蓄えられた電気を家庭でそのまま使えるわけではありません。電気自動車に使われているバッテリーは、専用コンセントで充電することができます。しかし、充電された電気を家庭で使えない理由は、電流の種類の違いにあります。EVやPHVバッテリーに蓄電された電気は直流であり、乾電池と同じ種類です。対して、家庭用の電気は交流なので、活用するには変換する必要が出てきます。
その変換する役割を担うのがV2H機器です。V2H機器を使えば、直流から交流へ、交流から直流へと変換することが可能になります。家庭用の予備電源として利用されているものといえば、蓄電池が一般的です。EVやPHVバッテリーは、蓄電池よりも容量がはるかに多いという特徴を持っています。つまり、V2H機器は、家庭全体をカバーできるだけの大きな電気を変換する能力を持っているのです。
V2H機器は「非系統連系」型と「系統連系」型の2種類に分けられます。V2H機器で対応できる電気の系統は、EVやPHVバッテリー、電力会社から提供される電気、そして太陽光発電で作られる電気です。「系統連系」型は、これら3つを同時に扱うことができ、V2H機器では主流となっています。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの役割
V2Hの主な役割は、自動車と家庭の電力システムを接続し、自動車のバッテリーを家庭での電力供給に活用することです。それ以外にも、V2Hにはさまざまな役割が期待されています。例えば、エネルギーの自己消費率を向上させ、持続可能なエネルギー利用の促進に寄与することなどです。以下では、それぞれについて詳しく解説します。
バックアップ電源の提供
まず、挙げられるのが停電時や非常時におけるバックアップ電源の提供です。自動車のバッテリーは、一定の容量を持っているため、家庭での使用に必要な電力を一時的に補完できます。つまり、万が一の際の非常用電源とすることが可能です。
需要と供給の調整
V2Hは、自動車のバッテリーを利用した家庭の電力需要と供給のバランス調整につながります。例えば、自動車が充電中で余剰の電力を持っている場合、その電力を家庭で利用すれば電力グリッドへの負荷を軽減できるでしょう。逆に、電力需要が増加し電力グリッドからの供給が不足している場合は、自動車のバッテリーから電力を供給することで需要を補えます。
エネルギーの貯蔵と活用
自動車のバッテリーを一時的なエネルギー貯蔵装置として活用することも、V2Hに期待されている役割の一つです。通常、自動車は日中や夜間に充電され、バッテリーへ余剰電力が蓄えられます。V2Hを使用して、この余剰電力を家庭の電力需要に活用すれば、再生可能エネルギーの効率的な利用やピーク時の負荷軽減などが期待できるでしょう。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの2つのタイプ
V2Hには、「非系統連系(Islanded mode)」と「系統連系(Grid-tied mode)」という2つの異なる接続方式があります。非系統連系は、停電時や非常時に自宅での電力供給を確保する際に便利です。一方、系統連系は外部の電力グリッドとの連携によって車両のバッテリーを効果的に活用できます。これにより、電力の需要と供給のバランスが取ることが可能です。どちらの方式を選べばよいのかは、個々のニーズや利用状況によって異なります。以下では、2つの接続方式について解説します。
非系統連系(Islanded mode)
非系統連系は、太陽光発電を設置していなかったり、設置していても太陽光発電を売電にのみ利用していたりする場合に適した接続方式です。非系統連系では、車両と家庭の電力システムが独立して動作します。つまり、車両のバッテリーから家庭の電力需要を供給する際、外部の電力グリッドとは接続されません。非系統連系では、自宅の停電時や非常時などに車両のバッテリーを利用して家庭の電力を供給することが可能です。また、再生可能エネルギー源(太陽光発電など)を組み合わせることで、車両と自宅の電力を再生可能なエネルギーで賄うこともできます。
系統連系(Grid-tied mode)
系統連系は、太陽光発電をすでに設置済みで発電した電気を自家消費している場合に使用できる接続方式です。系統連系では、車両と家庭の電力システムが外部の電力グリッドに接続されます。これにより、車両のバッテリーから家庭の電力需要を補うだけでなく、余剰の電力を外部の電力グリッドに供給することも可能です。系統連系では、外部の電力グリッドが安定している場合、家庭の電力需要を優先しながら車両のバッテリーが充電されます。逆に、家庭の電力需要が少ない場合や太陽光発電などから余剰の電力が発生した場合、その余剰電力は外部の電力グリッドに供給されるのが特徴です。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの導入メリットは?

貯めた電気は、使わずにいると少しずつ放電します。そのため、電気自動車を持っていても、乗らないときは蓄えた電気が無駄になってしまいます。V2H機器を導入すれば、EVやPHVバッテリーの電気を家庭用電源として有効活用できるので便利です。V2H機器があれば、蓄電池ではまかないきれない電力までカバーしてくれます。
とはいっても、実際にはどのような場面でメリットがあるのか、なかなかイメージできないかもしれません。V2H機器の導入を検討するには、さまざまな活用シーンや特徴を知っておく必要があります。そのうえで、自分に合っているか考えてみるといいでしょう。ここでは、V2H機器の便利ポイント6つを具体的にわかりやすく説明していきます。
1.災害時の非常用電源として使える
現代においては、何をするにも電気が必要です。電気がなければ、通常の生活だけでなく、情報をキャッチしたり連絡したりすることもできなくなります。地震や台風といった大規模な災害が起こったときに心配なのは停電です。乾電池式のラジオを非常用として常備している家庭もあるかもしれません。しかし、それだけではインターネットやテレビのように、詳細な情報を得るのは難しいでしょう。テレビを見たり、スマートフォンを充電したりするにも電気は必要です。
また、季節によっては空調が使えないことで健康上の問題も発生します。寒さだけでなく、夏の熱中症対策にも空調の利用は不可欠です。電気がないと、使えない調理器具も出てきます。もちろん、照明器具も使えませんし、日常生活を営むには何かと不便を強いられます。このような非常事態になったとき、EVやPHVバッテリーを電源として使えると便利です。電気自動車を持っている家庭であれば、そのバッテリーの電気をそのまま家庭用として使うことができます。
停電が長引くようなことがあっても、家庭内の電気をカバーできる電源があれば心配は要りません。照明や調理器具、スマートフォンやパソコン、エアコンなど、普段使っている電化製品のほとんどの電力がまかなえます。
2.V2Hは家庭用蓄電池よりも容量が大きい
災害時の停電は、実際にそのときになってみないと収束のタイミングはわからないものです。数時間で復旧することもあれば、停電が数日間に及ぶこともあります。万が一を考えて、家庭用蓄電池を用意している家庭もあるでしょう。しかし、せっかく非常用電源として備えていても、数時間しか使えないと結局困ってしまいます。家庭用蓄電池の場合だと、4~12kWhが一般的です。対して、V2H機器を利用すれば10〜100kWhの電力を確保できます。
数字を見てもわかるように、H2V機器による給電量は家庭用蓄電池の量をはるかに超えています。具体的には、車種ごとの容量にもよりますが、給電可能時間は100時間を超えるものも出ています。つまり、4日間程度使える電力を供給できるということです。大容量の車種であれば、数日間にわたって停電になっても安心できます。もちろん、必要な電化製品を気にせずに使うことも可能になります。
停電のとき、数時間程度しか予備電源が使えないのは心細いものです。エアコンのような電力を使うものは、どうしても我慢しなければなりません。しかし、暑い時期や真冬は、どうしてもエアコンの使用は欠かせません。その点、V2H機器があれば大容量のEVやPHVバッテリーの電力を使えます。不安を抱えながら不便な生活をすることなく、電気が復旧するまで快適に過ごせます。
3.EVやPHVバッテリーの充電がスピーディ
EVやPHVバッテリーは、通常は専用のコンセントから充電を行います。しかし、その場合、充電にやや時間がかかるのが難点です。すぐ車を使いたいのにバッテリー残量が少ないときは、面倒に感じる人も多いのではないでしょうか。車を充電するために、すぐ外出できないのは不便です。緊急で車を出したいときも対応することができません。V2H機器を経由してEVやPHVバッテリーに充電した場合、時間を早めることができます。200ボルトの家庭用コンセントと比べると、充電にかかる時間は半分程度です。
夜間に充電を始めておけば、翌朝には満充電になります。そのため、毎日通勤で電気自動車を使う人なら、帰宅後にV2H機器で充電しておけば、翌朝には問題なく乗ることができるでしょう。もしも、充電時間の部分で電気自動車の検討を迷っている人がいるなら、V2H機器の導入も併せて考えると解決につながります。
充電時間が短ければ、もしものときの予備電源としても安心して使えます。バッテリーの容量自体は大きくても、肝心の充電が間に合っていなければ余裕を持って使うのは無理な話です。乗った後はV2H機器を通して充電することを習慣にしておけば、いざ停電になったときも頼もしい予備電源になってくれるでしょう。災害時に使える蓄電池として考えたときも、充電時間が早いほうが便利で安心です。
4.電気代の節約が可能になる
V2H機器があれば、電気代の節約につながるのも大きなポイントです。電気会社の契約の中には、夜間は料金が安くなるプランもあります。夜間料金が安いプランで契約しておけば、寝ている間に充電することで車にかかる電気代を抑えられます。貯めた電気は、日中の走行はもちろん、家庭用電気として消費することも可能です。そもそも、1日の走行距離自体が少ないなら、大容量の蓄電池として利用するのもいいでしょう。
上手に活用していけば、年間単位で見たときに電気代を大幅に削減することができるでしょう。電気代の高騰で頭を悩ませている家庭なら、V2H機器の導入は思わぬ解決策になるかもしれません。電気代については、特に2023年度に入ってからも見直しがされています。少しでも節約をしたいと考える家庭は多いのではないでしょうか。車を走らせるためのコストとして考えたときも、深夜電力を使えばガソリン車より安くなる可能性があります。
電気は、生活に必要不可欠なものです。毎日使うものだからこそ、もっと費用を抑えていけば利用量を気にすることなく使えます。電気代を節約できれば、その分だけ他のこと、たとえば子どもの習い事やレジャー費などに費用を回せるようになるでしょう。
5.国や自治体の補助金制度が使える
補助金が活用できるのは、H2V導入の大きなポイントといっていいでしょう。補助金があれば、それだけ自己費用を抑えることができます。予算のことで導入を悩んでいたという場合でも、前向きに検討することができるでしょう。V2H機器の購入はもちろん、設置工事や電気自動車の購入にまで補助金の活用が可能です。
補助金は、自治体のものだと都道府県と市区町村の2種類があります。注意しておきたいのは、すべての自治体が制度を設けているわけではないという点です。まず、自分が居住する地域で補助金制度があるかどうか調べておくといいでしょう。また、制度があったとしても、先着順だったり期限が決まっていたりするので注意が必要です。もしも補助金が活用できる地域でも、気づいたときにすでに受付が終了していることもあります。その場合は、次年度まで待たなければなりません。
自治体だけではなく、国の補助金制度も利用できます。そのため、居住地の自治体で補助金がない場合でもあきらめる必要はありません。国の補助金が利用できれば、H2V機器の導入費用を抑えることはできます。2023年度の場合は、V2Hの補助金としての上限は115万円です。H2V機器の購入費と工事費をあわせた額ですが、かなり自己負担を抑えられるのではないでしょうか。なお、条件によっては自治体との補助金と併用できる点もうれしいポイントです。ただし、国の補助金も先着順となっているので注意しましょう。
6.太陽光発電の有効利用ができる
太陽光発電を有効利用できるのも、H2Vシステムのポイントの一つです。太陽光発電システムを設置しておけば、晴れた日の昼間は太陽光で発電し、その電気をEVやPHVバッテリーに貯めておくことができます。もしも、買い物用など通勤以外で使う車を検討しているなら、電気自動車にすると有効的に使えるでしょう。夜間は電気の安い電力会社の電気で充電するなど、使い方によってはかなり電気代を抑えられるかもしれません。
また、太陽光発電による余剰電気は、売電することで副収入として入ってきます。太陽光発電とV2Hを併用すれば、それだけ経済的なメリットは大きなものとなるでしょう。電気代だけで考えるより、家計費全体として考えたときも大幅な節約が期待できるでしょう。太陽光という自然のパワーを活用することで、エコにもつながります。H2Vシステムだけでなく、太陽光発電に興味を持っている家庭にも向いている使い方です。
すでに太陽光発電を取り入れていれば、H2V機器の導入によってさらに有効的に使えるかもしれません。トータル的に無駄なく電力を使う手段として、太陽光発電とH2Vの併用は有効なポイントです。
▶ 太陽光発電の価格と商品比較
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2H機器を導入する際に注意しておきたいこと

ここまで説明してきたように、V2Hは便利でメリットが多いシステムです。電気の節約も可能ですし、いざというときの予備電源としても活用できます。しかし、だからといって無条件で導入できるわけでもありません。上手に活用するには、いくつか注意しておきたいポイントもあります。V2H機器を導入してから知って損をした、ということがないようにしておきましょう。
V2H機器の導入で失敗を避けるには、まず必要な条件を事前に把握しておくことです。自分の家や利用条件に合っているかを理解しておかなければなりません。そのうえで上手に活用すれば、快適な暮らしにつなげることができます。ここでは、V2H導入における5つの注意点を解説していきます。
対応車種であることを確認しておく
電気自動車であれば、どれでもV2Hに対応しているわけではありません。EVやPHV車をすでに所有している人は、まずこの点に注意が必要です。V2Hに対応する車種は限られています。新規での購入や乗り換えをする際は、その前に対応車種をしっかり把握しておきましょう。ただし、限られるといっても、2023年6月時点では国内メーカーのほとんどがV2H対応車種を販売しています。
車を買う際、自分の好きなメーカーなどこだわりを持っている人は多いかもしれません。そういった場合でも、ほとんどのメーカーから出ているので安心です。ただし、同じメーカーの電気自動車でも対応可能な車種と非対応の車種に分かれています。もしも気になる車種があっても対応していない可能性もあります。後で失敗に気づくことのないよう、まず各メーカーのV2H対応車種を確認しておきましょう。
それぞれの公式サイトで確認するのもいいですし、電子カタログなどで詳細をチェックする方法もあります。車としての使い勝手や乗り心地などを知るためには、ディーラーで担当者に相談するのもいいかもしれません。車種によっては試乗できるものも出ています。まずネットで情報を集め、気になる車種を絞ってから実際に見て話を聞いたり試乗したりすれば失敗を避けられます。
V2Hの対応車種の詳細はこちら
バッテリーの劣化が通常使用よりも早まる
EVやPHVのバッテリーは、家庭用蓄電池と比べれば耐久性は高いものになっています。それでも、頻繁に使っていれば、それだけ劣化を早めることは確かです。車として使う場合よりも、家庭用電源としても使うほうがバッテリーの寿命は多少縮まります。バッテリーの劣化は、最大容量が減るという形で表れてきます。これは、充電式のバッテリー全体にいえることで、車でも同じです。車として優先的に使いたいなら、H2Vの導入は向いていないかもしれません。この点は、導入前に慎重に考えておくといいでしょう。
走行以外の使用回数が大幅に増えると、その分劣化して最大容量は徐々に減少していきます。例えば、はじめはフル充電で60時間使えたとしても、劣化によって50時間ほどになるかもしれません。ただし、バッテリーの劣化を防ぐ使い方もあります。その秘訣は充電のタイミングです。最大容量の20~30%程度まで使用してから充電すると、劣化速度を抑えることが可能です。
しかし、充電の仕方で劣化を防ぐことはできても、永久的に同じバッテリーを使えるわけではありません。車種や使用頻度によって変わりますが、いずれバッテリーの交換は必要になります。そのときの費用についても、事前に理解しておきましょう。
瞬間的に停電が起こる場合もある
V2H機器の利用で念頭に置きたいのは、瞬間的な停電です。V2H機器を通して給電しているときは、電力会社の電気を同時に使うことができません。そのため、切り替え時に瞬間的な停電が発生するのです。必ず停電が起こるというわけではありませんが、可能性として理解しておくといいでしょう。停電が起こるのは、EVやPHVのバッテリーからの給電量より家庭で使う電力量が上回る場合です。
停電といってもほんの一瞬ですが、使っているものによっては影響を受ける場合もあります。瞬間的な停電を避けるには、EVやPHVのバッテリーの電気を使っているときに消費電力が大きくなりすぎないことも注意点の一つです。特に、パソコンを使っているときは注意したほうがいいでしょう。例えば、テレワークなどで重要なデータを扱っているときは消失する危険をともないます。
切り替え時に作業することがないよう、一旦保存して終了させておくなどの工夫は必要です。切り替わってから再び作業を開始すれば、リスクは回避できます。パソコンのような記憶媒体のある電子機器は、突然の停電で不具合が発生する可能性があるので、トラブルを防ぐにはUPS(無停電電源装置)を使うなどの対策をしておくのもいいでしょう。
導入するときに費用がかかる

H2Vを導入するには、それなりに初期費用がかかることも、注意しておきたい点です。これからすべて揃える場合は、電気自動車の購入費用も必要になってきます。メーカーや車種によって価格は変わってきますが、手ごろなものでも車両価格は400万円前後が相場です。ただ、中古車から選ぶようにすればその分費用を抑えることはできます。その場合は、H2V対応車種であるかどうかの確認も忘れないように注意しましょう。年式によっては、同じ車種でも対応していないケースもあります。
すでに対応車種を所有している場合でも、V2H機器は新たに購入しなければなりません。H2Vの価格相場は、50~100万円程度です。本体の購入だけでなく、導入するには設置費用もかかります。工事は住居のタイプで異なりますが、戸建てだと30万円以上、集合住宅の場合なら50万円以上を見ておく必要があります。
H2Vの導入によって、電気代の節約は見込めますし、災害時の停電に備えることもできます。それでも、導入費用に対してどれくらいコストバランスがとれるかは慎重に判断しなければなりません。ただし、先述したようにH2Vは導入時に補助金を活用できます。補助金を使えば、費用を安く抑えられます。H2V機器や工事費用、さらに車の購入にも補助金の利用は可能です。実際にはどれくらい安くなるのか事前に試算したうえで、経済的にメリットがあるかどうかを把握しておきましょう。
設置するには一定の条件が必要
H2V機器の設置には、欠かすことができない条件があります。EVやPHVバッテリーから給電するとき、家と車を有線でつながなければなりません。そのため、まず自宅と駐車場が隣接していることが条件になってきます。建物のすぐ近くに車を置けるという点で考えれば、戸建て住宅のほうが設置には有利です。しかし、戸建て住宅でも、駐車場が建物から離れていては使えません。また、同じ敷地内に駐車場があっても、建物との間に物置があるなどの条件があってはH2Vを設置できません。その点には十分注意をする必要があります。
集合住宅でも設置は可能ですが、その場合も条件は同じです。1階部分の部屋であり、駐車場がすぐ側であることが条件になってきます。車を置くだけでなく、十分な設置スペースも必要です。つまり、H2Vの導入には、建物の近くに車を停めるスペースとV2H機器を設置するだけの広さの確保が必要になります。
H2Vの導入を検討するには、まずこの条件をクリアしているかどうか考えることが重要です。これから戸建て住宅の購入を検討しているなら、この条件を視野に入れておいたほうがいいでしょう。その前に、実際にはどれくらいのスペースがあればいいのか考えておく必要もあります。駐車場として車の出し入れがしやすいことも忘れてはいけません。暮らしを快適にするためにも、H2Vの導入を考えながら総合的に判断することが大切です。
▶ V2Hの商品比較・メリットデメリット
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの導入方法
V2Hを導入する際には、施工業者へ設置を依頼しなければなりません。ここでは、どのような手順になるのかについて解説します。
施工業者へ依頼
V2Hは、複雑な屋内配線が必要となるため、自分で設置することはできません。また、電力会社からの承諾も必要になるため、設置はV2H機器の販売・施工を請け負っている施工業者に依頼することが必要です。新築の場合は、ハウスメーカーがこれらの依頼を代行してくれる場合もあります。代行してもらえる場合でも、設置に伴う保証などについては事前に確認にしておきましょう。
業者による現地調査
施工業者へ依頼すると、現地調査が行われます。主な確認事項は、以下の通りです。
・V2H機器や分電盤の設置予定場所
・メインブレーカーの容量や種類と変更の有無
・分電盤からV2H機器を設置する駐車場までの配線ルート など
確認した現地の状況によって、V2H機器の設置場所を決めていきます。また、この調査に基づいて工事費の見積もりも行われるため、価格などで不自然なところがないかよくチェックしましょう。
工事の契約
現地調査が完了したあとは、業者と工事の契約を結びます。工事を開始するためには、電力申請や事業計画変更申請に関する許可申請が必要です。この許可は、V2H機器を家庭で使用するためのものとなります。許可が下りるまでの期間は、太陽光発電が設置されていれば約1~2カ月、太陽光発電が設置されていなければ約5~6カ月かかるのが一般的です。
工事の竣工
許可が下りたあとは、工事が始まります。工事の主な内容は、以下の通りです。
・あらかじめ指定していた場所へのV2H本体の設置
・基礎部分との固定作業
・充電ケーブルや分電盤とV2H間の配線工事 など
V2Hの設置と配線工事まで完了すると、次は各種計器類を用いて接続方法にミスがないか、漏電していないか、ショートしていないかなどを確認します。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hを選ぶ際のポイント

V2H機器は、さまざまな会社が販売していて、それぞれに特徴があり価格や機能も多岐にわたります。そこで、ここではV2Hを選ぶ際に考慮しておきたいポイントについて解説します。
操作性
V2H機器によって操作性は異なります。それぞれの機器には、独自の操作パネルや設定方法があり、接続方法によっても操作性が異なるのが一般的です。そのため、V2Hシステムを導入する際にはメーカーが提供する操作マニュアルやガイドラインを参照し、正確な操作方法の確認が大切になります。自分が使いやすい機器を選ぶことができれば、V2Hシステムをより快適に利用できるでしょう。
設置場所
一般的なV2H機器のサイズは、縦85cm×横80cm×奥行35cm程度です。機器を設置することで、その分屋外スペースが狭くなる点は押さえておきましょう。また、設置場所に十分なスペースがあるかどうかもしっかりと確認しておくことが重要です。
停電時に対応しているかどうか
V2H機器が停電時に対応しているかどうかも確認しておきましょう。停電時に電気を供給できる範囲もV2H機器によって異なります。バッテリーバックアップ機能やスイッチオーバーの自動化機能、電力制御機能についてよく把握しておきましょう。これらは、メーカーが提供する製品仕様や操作マニュアルで確認できます。
価格
V2Hの導入費用は、一般的に機器費用として約50万〜100万円、設置費用として約30万〜40万円かかります。決して安い買い物ではないため、かかるコストと得られるメリットをしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。地域によっては、月額で使用できる場合もあります。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hに関する補助金
V2Hを導入する際には、国や自治体から補助金が出る場合があります。そのため、自分が住んでいる地域の自治体で補助金制度があるかについては、あらかじめ確認しておきましょう。ここでは、国が行っている補助金事業について詳しく解説します。
CEV(Clean Energy Vehicle)補助金
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)といったクリーンエネルギー車両の導入を促進するために政府や地方自治体などが提供する補助金です。もともとは、これらクリーンエネルギー車両の製造コストが大きく、ガソリン車と比べて車両価格が高額となりがちであったことから、その金額の差を縮めて購入を促す目的で始まりました。2022年11月現在の時点で電気自動車(EV)の補助金上限額は92万円、プラグインハイブリッド車(PHEV)の補助金上限額は55万円です。
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)などの導入と、それらの普及に不可欠なインフラの整備等を支援する目的で経済産業省が行っている補助金です。この補助金は、クリーンエネルギー車両と充放電設備や外部給電器の両方を同時に購入する個人が対象者となります。補助金の上限額は、電気自動車(EV)が上限80万円、プラグインハイブリッド車(PHEV)が上限40万円、燃料電池自動車(FCV)が上限250万円です。
充放電設備の設備費は、2分の1補助で上限75万円、工事費は定額補助で上限40万円(個人)となっています。また、外部給電器の設備費は3分の1補助で上限50万円です。
再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業
環境省は、再生可能エネルギー電力と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)または燃料電池自動車(FCV)を活用したドライブを「ゼロカーボン・ドライブ」と名付けて支援しています。その一環として行われている補助金事業が「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」です。
電気自動車は上限80万円、プラグインハイブリッド車は上限40万円、燃料電池自動車は上限250万円が補助されます。また、オプションとして「充放電設備/外部給電器」を購入する場合、災害時等における地域への貢献等を要件として設備購入費・工事費の一部が補助されます。
▶ CEVのV2H補助金の詳細はこちら
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
V2Hの対応車種
V2H対応車種その1:三菱
三菱では、電気自動車(EV)で3種、プラグインハイブリッド車(PHEV)で2種がV2Hに対応しています。電気自動車(EV)で対応しているのは、eKクロス EVと2010年以降のi-MiEV、MINICAB-MiEV(バン・トラック)です。eKクロス EVは蓄電容量20kWh、1回の充電あたりの走行距離はWLTCモード(国土交通省審査値)で180kmとなっています。2010年以降のi-MiEVには、蓄電容量が10.5kWhのものと16kWhのものがあり、航続距離は10.5kWhで120km、16kWhで180kmです。
MINICAB-MiEVの場合、バンの蓄電容量は10.5kWhと16kWhの2種類、トラックの蓄電容量は10.5kWh、1回の充電あたりの走行距離は最大120kmとなっています。プラグインハイブリッド車(PHEV)のH2V対応車は、アウトランダーPHEVとエクリプスクロスPHEVです。アウトランダーPHEVの蓄電容量は、年式によって異なり、12kWh、13.8kWh、20kWhの3種類があります。WTLCモードでのEV走行換算距離は83kmです。エクリプスクロスPHEVの蓄電容量は13.8kWh、航続距離はWTLCモードで57.3kmとなっています。
V2H対応車種その2:日産
日産では、4種の電気自動車(EV)を生産しており、そのどれもがV2H対応車です。電磁気自動車のパイオニアと呼ばれているリーフの蓄電容量は、24kWh、30kWh、40kWh、62kWhの4種類があります。1回の充電あたりの航続距離はバッテリーのみで350〜550kmです。SUVタイプのアリアもV2Hに対応しており、蓄電容量は66kWhと91kWhの2種類があります。とりわけ91kWhのアリアは、2022年時点で蓄電容量が最も多い国産車です。航続距離は、軽規格のサクラもV2Hに対応しています。蓄電容量は20kWh、航続距離は最大640kmです。
サクラは、先述した三菱のeKクロス EVの姉妹車で、商用バンであるe-NV200もV2Hに対応しています。蓄電容量は24kWhと40kWhの2種類があり、1回の充電走行距離はWLTCモードで180kmです。
V2H対応車種その3:トヨタ
トヨタは、bZ4Xと2019年5月以降のプリウスPHV、MIRAIの3車種がH2Vに対応しています。bZ4Xは、トヨタ初の量産BEVで蓄電容量は71.4kWh、満充電時の走行距離はFWDが559km、4WDが540kmです。プラグインハイブリッド車のプリウスPHVは、2019年5月以降の5人乗りモデルからV2Hに対応しています。蓄電容量は8.8kWh、1回の充電あたりの走行距離は68.2kmです。ただし、2023年にモデルチェンジされたプリウスPHEVはV2Hには対応していないので注意しましょう。燃料電池車のMIRAIも、停電時限定ではあるもののV2Hに対応しています。
V2H対応車種その4:ホンダ
ホンダでは、量産型電気自動車である都市型コミューターHonda eがV2Hに対応しています。蓄電容量は35.5kWh、航続距離はWLTCモードで259kmです。モダンかつ親しみやすいデザインが人気となっています。
V2H対応車種その5:マツダ
マツダでは、MX-30 EVモデルとCX-60 PHEVがV2Hに対応しています。MX-30 EVモデルの蓄電容量は35.5kWh、1回の充電走行距離は256kmです。CX-60 PHEVの蓄電容量は17.8kWh、満充電での走行可能距離は74kmとなっています。
V2H対応車種その6:スバル
スバルでは、トヨタのbZ4Xの姉妹車である電気自動車ソルテラがV2Hに対応しています。蓄電容量は71.4kWh、1回の充電走行距離は、ET-SS(FWD)が567km、ET-SS(AWD)が542km、ET-HSが487kmです。
V2H対応車種その7:レクサス
レクサスでは、RZ450eとUX300eの2種がV2Hに対応しています。RZ450eの蓄電容量は71.4kWh、1回の充電あたりの走行可能距離は494kmです。UX300eは、2023年3月30日以降のモデルからV2Hに対応しています。蓄電量料は72.8kWh、1回の充電あたりの走行可能距離は512kmです。
V2H対応車種その8:ベンツ
ベンツのV2H対応車種は、EQSとEQE、S 580e 4MATIC longの3種です。EQSは、通常モデルのEQS 450+だけでなくAMGモデルのMercedes-AMG EQS 534MATIC+もV2Hに対応しています。蓄電容量は107.8kWhで、2023年4月現在で世界最大の蓄電量となっています。航続可能距離は、EQS 450+が700km、Mercedes-AMG EQS 534MATIC+が601kmです。
EQEもEqsと同じくEQE 350+とAMGモデルのMercedes-AMG EQE 534MATIC+の2モデル展開を行っており、どちらもV2H対応です。蓄電容量はどちらも90.6kWhで、航続距離はEQE 350+が624km、Mercedes-AMG EQE 534MATIC+が505kmです。S 580e 4MATIC longは、MP202301以降のMPがV2Hに対応しています。蓄電容量は28.6kWh、航続距離は約90kmです。
V2H対応車種その9:ヒュンダイ(ヒョンデ)
ヒュンダイ(ヒョンデ)では、IONIQ5がV2Hに対応しています。蓄電容量は58kWhと72.6kWhの2種類があります。58kWhのバッテリー搭載車の航続可能距離は2WDで498kmです。72.6kWhのバッテリー搭載車の場合、2WDだと618km、4WDだと577kmが航続可能距離です。IONIQ5は、実店舗を持たずにネット上でのみ販売する販売手法でも大きな注目を集めています。
V2H対応車種その10:BYD
中国企業のBYDは、電気自動車の販売台数世界一を誇る自動車メーカーです。BYDでは、4種のV2H対応車を販売しています。そのうちe6とJ6、K8は商用車のため、聞いたことがない人も多いのではないでしょうか。一般向けモデルは、ATTO3で蓄電容量は58.56kWh、1回の充電走行距離は約485km(WLTC)です。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
エコ発電本舗ならV2Hを安心でお得に導入できる!
V2H機器を自宅に設置しておけば、もしも災害が起こったときの緊急電源として使用できます。万が一停電が数日に及ぶことがあっても、予備電源として家庭でも電気を使えます。車として使わないときはバッテリーの蓄電を利用するなど、日常的に電気代を節約することも可能です。電気自動車のバッテリーは家庭用蓄電池より容量がはるかに大きく、予備電源としても十分でしょう。太陽光発電との併用も可能ですし、有効的な使い方ができる点も便利です。災害時の備えや、節電対策として考えるならH2Vシステムの導入は有効な手段といえます。
しかし、電気自動車であればどれでも対応できるわけではありません。便利な反面、対応機種が限られるなどの注意点もいくつかありますし、設置可能な条件などもあります。上手に活用するには、V2H機器のメリット・デメリットも知っておくことが重要です。そのほうが、導入してからの失敗も避けられますし、家庭や目的に合った導入方法を考えることもできます。
エコ発電本舗なら、業界最安値でH2Vシステムの導入が可能です。提携しているのはメーカーが推奨する工事店だけなので、工事品質に不安を感じることもありません。設置後の故障についても迅速に対応してくれて安心です。価格や商品の特徴、対応車種についてさらに詳しく知りたい人はこちらもチェックしてみましょう。