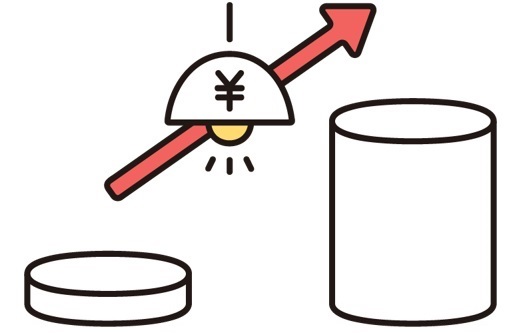
毎月の家計簿をチェックしていると、電気代の値上がりが気にかかる人も多いのではないでしょうか。電気は生活に欠かせませんが、料金が上がると家計は大きな影響を受けます。では、私たちが日々の生活の中でできる対策にはどのようなものがあるのでしょうか。そこで今回は、電気料金の現状や今後の見通し、そして私たちにできる節電対策などについて解説していきます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
2023年の日本における電気料金の動向
2023年は、日本の電力業界にとって大きな変動の年となりました。背景には、国際的な燃料価格の変動や国内の発電事情、さらに政府の補助政策の影響があります。
値上げの動き
2023年4月には、東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の5社が家庭向けの電気料金を引き上げました。さらに、北海道電力と東京電力も6月に値上げを実施しています。
これらの値上げ幅は、**2022年11月の料金と比較して14%~最大42%**に達し、利用者に大きな影響を与えました。背景には、原材料費や電力調達コストの高騰、燃料調整費の増加などがありました。
値上げを回避した電力会社
一方で、関西電力・中部電力・九州電力の3社は値上げを行いませんでした。理由は、原子力発電所の稼働が比較的順調であり、火力発電の燃料価格高騰による影響を抑えられたことや、競争力維持のためとされています。
一時的な値下げとその背景
2023年8月には、大手電力会社が家庭向け電気料金を一時的に値下げしました。これは、LNG(液化天然ガス)や石炭といった燃料価格の下落が背景にあります。
しかし、6月に行われた大幅な値上げの影響が残っており、依然として料金水準は高止まりしています。
政府の「激変緩和措置」とその終了
2022年の電気代高騰を受け、政府は「激変緩和措置」を導入し、電気代の一部を補助してきました。
しかし、2023年10月から補助額が縮小され、さらに2024年1月には措置が終了する見込みです。その結果、10月には大手電力10社が再度値上げを実施し、標準的な家庭の電気代は642円~1024円程度の値上がりとなりました。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
電気料金が値上げされる理由とは?

電気料金値上げの背景には、さまざまな要因が絡み合っています。ここでは、電気料金が値上げされる理由を、影響を与えている要因とともに紹介していきます。
燃料価格が高騰しているから
電気料金の上昇には、国際的な燃料価格の高騰が大きく影響しています。ここでは、その要因を整理して見ていきましょう。
世界経済の回復による需要増加
新型コロナウイルスの影響で一時的に落ち込んでいた世界経済が回復に向かうにつれ、原油需要が急速に増加しました。その結果、原油価格が上昇し、火力発電のコスト増に直結しました。日本は石油火力を含む化石燃料への依存度が高いため、この影響を強く受けています。
天然ガスと石炭価格の変動
日本の電源構成では、天然ガス(LNG)と石炭の割合が大きいのが特徴です。これらの価格が高騰すると、電気料金に直結します。とくに天然ガスはドル建てで取引されるため、為替レートの影響も受けやすい構造となっています。
地政学リスクによる供給制約
さらに、2022年以降のロシアによるウクライナ侵攻が世界のエネルギー市場に大きな打撃を与えました。ロシアは世界有数の化石燃料輸出国であり、経済制裁や輸出制限の影響で供給が不安定化。これが燃料価格をさらに押し上げる要因となりました。
総合的な影響
● 世界経済の回復 → 需要増
● 為替変動 → 輸入コスト増
● ロシア制裁 → 供給制約
これらが重なり合って、電力会社の発電コスト増大 → 電気料金の値上げにつながっているのです。
国内の電力供給量が低いから
電気料金の値上げには、燃料価格の高騰だけでなく、国内の電力供給量そのものが減少していることも大きな要因となっています。背景を詳しく見ていきましょう。
原子力発電の停滞と影響
日本の電力供給量が低下している大きな要因は、2011年の東日本大震災以降に続く原子力発電所の停止です。震災前は全国の電力の約4分の1を担っていた原子力ですが、安全性の問題から稼働が制限され、2020年にはわずか数%にまで縮小しました。この急激な減少は、日本の電源構成を根本から変えてしまいました。
火力発電の縮小と課題
原子力の穴を埋めてきたのが火力発電ですが、近年は維持コストの高さや設備の老朽化により、休止や廃止が増加しています。さらに電力自由化による競争激化で採算が悪化し、事業としての継続が難しいケースも目立ちます。加えて、火力はCO2排出が多いため、環境負荷の面からも縮小が求められている状況です。
再生可能エネルギーの導入と限界
再生可能エネルギーは導入が進んでいますが、太陽光や風力は天候に左右されるため、安定した電源とはいえません。蓄電池や送電網の整備が進んでいない現状では、原子力や火力の代替にはまだ不十分です。これが、供給力全体の低下につながっています。
需給バランス悪化と電気料金の上昇
原子力と火力の縮小、再エネの不安定さが重なり、国内の電力供給は逼迫しました。その結果、需給バランスが不安定となり、電力調達コストが上昇。最終的に家庭や企業が支払う電気料金の値上げへとつながっています。
再エネ賦課金が値上がりしているから
FIT制度と再エネ賦課金の仕組み
再生可能エネルギーの導入を後押しするため、政府は「固定価格買取制度(FIT)」を導入しました。この制度は、太陽光発電などの再生可能エネルギーで生み出された電気を、電力会社が一定価格で買い取る仕組みです。その費用をまかなうために電気料金に上乗せされているのが「再エネ賦課金」であり、一般家庭から企業まで、電気を使うすべての利用者が負担しています。
急激に進んだ普及と単価の上昇
2010年代に入ると、産業用太陽光発電を中心にFITを利用した設備の導入が急速に進みました。その結果、再エネ賦課金の単価は2012年の0.22円/kWhから2022年には3.45円/kWhへと約15倍に上昇しています。表面上はわずかな数字の変化に見えるかもしれませんが、年間で大量の電気を使用する企業にとっては、数十万から数百万円規模のコスト増加につながっています。
普及と負担のバランスという課題
再エネ賦課金の上昇は、再生可能エネルギー普及に必要な投資である一方で、電気料金値上げの一因ともなっています。環境への貢献と消費者負担のバランスをどう取るかが、今後のエネルギー政策における大きな課題といえるでしょう。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
電気料金の値上げで1カ月の電気代はどのくらいになる?
東京電力「スタンダードS」プランを前提としたシミュレーション
ここでは、東京電力の「スタンダードS」プランを例に、4人家族が平均的な電力使用量として月300kWhを消費するケースを想定しました。電気料金の計算は「基本料金+電力使用量金+燃料調整費+再エネ賦課金」という式に基づいています。再エネ賦課金については、2023年4月が3.45円/kWh、同年5月から2024年4月までは1.40円/kWhの単価を使用しました。
値上げ前の電気代
値上げ前の試算では、基本料金(295.24円×30日)、電力使用量金(26.49円×300kWh)、再エネ賦課金(3.45円×300kWh)を合算し、月額は1万7974円となりました。
値上げ後の電気代
一方、値上げ後は基本料金は同じながら、電力使用量金が36.60円×300kWhに引き上げられ、再エネ賦課金が1.40円×300kWhとなります。その結果、合計は2万167円となりました。
値上げによる家計への影響
この比較から、1カ月あたりの電気代は2193円の増加、年間換算では2万6318円の増加となります。電気料金の値上げが、一般家庭の家計に与える影響がいかに大きいかが明らかです。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
政府が支援する「激変緩和措置」について
電気料金値上げによる家計への影響を緩和するため、政府は「激変緩和措置」という支援策を実施しています。この措置は、電気料金の急激な上昇を抑え、消費者の負担を軽減することが目的です。ここでは、激変緩和措置の内容を紹介し、政府の支援策が私たちの日常生活にどのように役立っているのかを解説していきます。
激変緩和措置の概要
激変緩和措置とは、家計に大きな負担をもたらす電気料金値上げに対応するために、政府が2023年1月から開始した補助制度のことです。この措置は、経済全体に対する総合的な経済対策の一環として導入されており、電気料金の急激な上昇をやわらげることを目的としています。激変緩和措置による電気料金の値引きが適用されるのは、補助事業に参加する小売電力会社です。この制度にもとづき、適用を受ける小売電力会社と契約している顧客の検針票には、「政府支援による使用量×〇〇円の値引き」と表記されます。
当初の補助概要は、低圧契約の家庭等は1kWhあたりマイナス7円、高圧契約の企業等は1kWhあたりマイナス3.5円です。2023年9月使用分に限り、これらの単価は半額になっています。この激変緩和措置は、電気料金の値上げに伴う消費者への影響を緩和し、経済全体の安定を図るための重要な政策といえるでしょう。
補助期間の延長
当初、2023年9月分までで終了が予定されていた「激変緩和措置」ですが、その補助期間が2024年1月まで延長されることが決定しました。しかし、この延長には変更点があります。具体的には、11月から2024年1月までの値引き率は、10月の電気料金(9月使用分)と同じに設定され、補助金額が半分となることです。補助期間の延長は、電気料金値上げの影響を受ける消費者にとっては一定の安心材料となるでしょう。しかし、補助額が半分に減少することにより、実際には9月の電気料金よりも割高な状況が生じる可能性があるので注意が必要です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
電気料金の値上げ傾向はいつまで続くの?
電気・ガス価格激変緩和対策事業の概要
2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」には、電気・都市ガス料金の高騰を抑えるための「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が盛り込まれています。この事業は、燃料価格上昇による一般家庭の負担を軽減することを目的としています。ただし、対策には期限が設けられているため、恒久的な効果を期待することはできません。
国際情勢がもたらすリスク
ウクライナ情勢の長期化により、燃料価格の不安定さは2023年以降も続く可能性が高いとされています。さらに、ウォールストリートジャーナルや日経新聞では、最近のパレスチナ・イスラエル戦争が天然ガス市場に大きな影響を与える可能性を報じています。日本の火力発電は天然ガスへの依存度が高いため、国際的な価格上昇は電気料金の再値上げにつながるリスクをはらんでいます。
制度面が電気料金に与える影響
インボイス制度の導入や電力買取コストの増加は、電力会社にとって消費税負担の増加要因となります。また、再生可能エネルギー導入を支援するFIT制度は、一定期間固定価格での電力買取を電力会社に義務づけています。この仕組みにより、買取コストが電気料金や再エネ賦課金の値上げにつながる可能性があります。
今後の家計への影響
こうした国際情勢や制度的要因が重なることで、今後も電気料金が上昇傾向をたどる可能性は否定できません。単月で見れば負担額は小さく感じられるかもしれませんが、物価全般が上昇している状況下でのさらなる電気料金の値上げは、家計にとって大きな打撃となることが予想されます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
電気料金値上げの対策としてできること

電気料金が値上げされるなかで、私たちにできる対策は何でしょうか。ここでは、電気料金値上げに対応するための具体的な対策や、日々の生活の中で実践できる節電のコツについて紹介していきます。
家電の使い方を工夫して節電する
電気料金値上げに直面するなかで、家電の使い方を工夫して節電に取り組むことはとても効果的です。日々の生活の中での簡単な工夫によって、消費電力を減らして節電につなげることができます。エアコンの使用では、無理のない範囲で設定温度を調整しましょう。使用していない電気製品のコンセントを抜いておくことも大切です。また、使っていない部屋の照明は消しましょう。冷蔵庫の詰め込み過ぎや頻繁な開閉を避けることで、無駄な電力消費を抑えることも可能です。掃除をする前に片付けをし、効率的に掃除機を使うことも効果があります。
さらに、テレビの画面の明るさを適切に設定し、使用していないときには消すことで節電につながります。これらの小さな工夫が、節電するための一歩となり、家計の節約に役立つでしょう。
省エネ家電に買い替える
電気料金値上げに対する有効な手段として、省エネ性能に優れた家電製品への買い替えがあげられます。家電は、新しくなるにつれて省エネ性能が高まる傾向があるため、買い替えることで電気代の削減が可能です。経済産業省エネルギー庁の調査によれば、10年前のエアコンと比べると、年間消費電力量を約17%削減できるとされています。また、冷蔵庫やテレビなど、消費電力が多い家電製品では、省エネ性能に優れたモデルに買い替えることで40%以上の省エネが実現可能です。さらに、照明を一般的な電球からLEDへ変更することにより、約86%の省エネとなります。
このように、10年以上使用している古い家電製品を持っている場合、タイミングが合えば省エネ性能の高い製品への買い替えを検討するとよいでしょう。
プランや電力会社を見直す
電気料金の値上げに対抗するためには、契約しているプランを自分の使用状況に合ったものに見直すことが有効です。電気の使用量や利用する時間帯によって最適なプランは異なるため、ライフスタイルに合わせて検討することが大切です。電力会社各社は多様なプランを提供しており、適切に選ぶことでコストを抑えられます。
電力会社切り替えという選択肢
電力自由化によって、消費者は複数の電力会社の中から契約先を選べるようになりました。電気料金の値上げ対策として、電力会社を切り替えることも有効な手段です。ただし、すべての住宅で自由に切り替えができるわけではありません。
賃貸住宅での注意点
賃貸住宅や集合住宅に住む人は、まず切り替えが可能かどうかを確認する必要があります。多くの場合は切り替えが可能ですが、「一括受電」を採用している建物では、入居者が個別に電力会社を変更できないケースがあります。そのため、契約を検討する前に管理会社や大家に確認することが重要です。
供給エリアの確認
電力会社には全国展開している企業もあれば、地域限定でサービスを提供している会社もあります。たとえ魅力的な料金プランがあっても、自宅が供給エリア外であれば契約できません。興味のある電力会社を見つけたら、まず供給エリアを調べることが欠かせません。
太陽光発電を導入する
電気料金値上げの影響を軽減するための対策として、家庭向け太陽光発電システムの導入が効果的といえます。自家発電によって電気料金の負担を大きく削減できるのです。たとえば、太陽光発電システムと蓄電システムを併用することで、昼間に発電した電力を夜間にも使用できます。このように、必要な電力を自家発電でまかなえれば、電力会社からの電気の購入は不要となるでしょう。
さらに、太陽光発電システムを導入すれば、生成した電力を売ることも可能です。固定価格買取制度(FIT制度)を活用すると、一定期間固定価格で電力を買い取ってもらえるため、安定した収入源となることも期待できます。しかし、太陽光発電設備の導入には、初期費用がかかります。投資の回収期間や発電効率など、導入前にしっかりとしたシミュレーションを行うことが推奨されます。
▶ 太陽光発電の価格と商品比較
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電なら「エコ発電本舗」に相談しよう!
電気料金値上げの対策として太陽光発電の導入を考えているのなら、「エコ発電本舗」がおすすめです。エコ発電本舗は、インターネット販売に特化しており、業界最安水準の価格設定となっています。また、品質の高さも大きな魅力の1つです。施工技術の質が高く、評判のよい工事店のみを厳選して提携していますので、安心して太陽光発電システムの導入を検討できます。さらに、エコ発電本舗では、業界最長となる15年間の工事保証を提供しているため、長期にわたる安心感を得られるでしょう。見積もりの依頼は無料なので、気軽に相談できます。
なお、2023年最新の太陽光発電の価格相場やメリット・デメリットに関する詳しい情報が、エコ発電本舗のウェブサイト(https://www.taiyoko-kakaku.jp/product
)に掲載されています。太陽光発電の導入を検討している人は、ぜひ、ウェブサイトを訪れてみてはいかがでしょうか。電気料金の値上げへの対策として、太陽光発電システムの導入は非常に有効な選択肢の1つです。エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
家庭でできる対策を実践して電気代の値上げに備えよう!
電気代が値上がりしているからといっても、暮らしに密接に入り込んでいる電気の使用を大幅に減らすことは現実的ではありません。そのためにも、この記事で紹介した家庭でできる節電対策、たとえば省エネ家電への買い替えや電気料金プランの見直し、そして太陽光発電システムの導入などを実践しつつ、電気代の値上げに備えていきましょう。




























