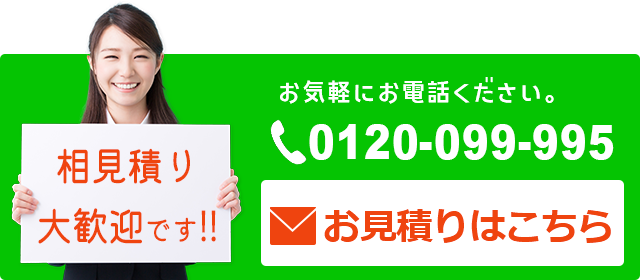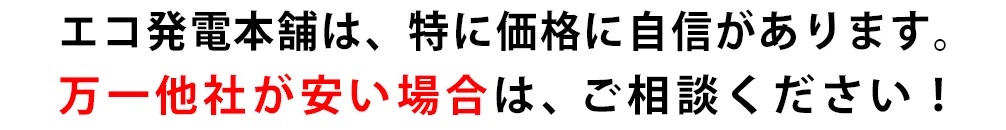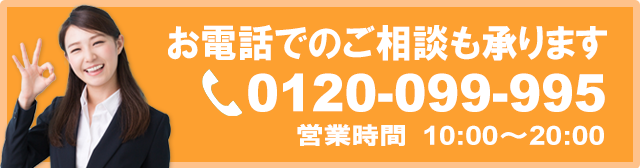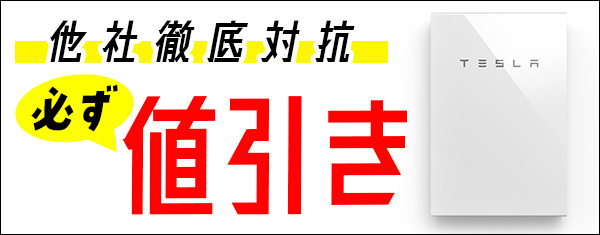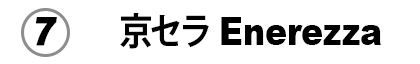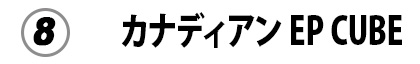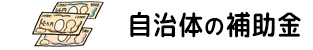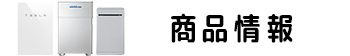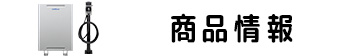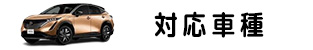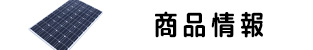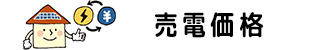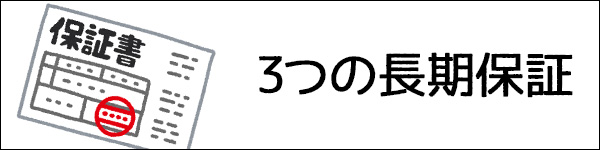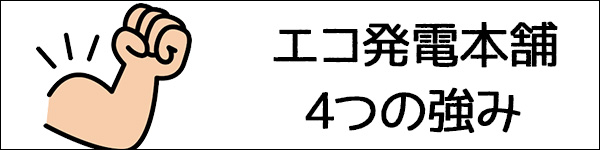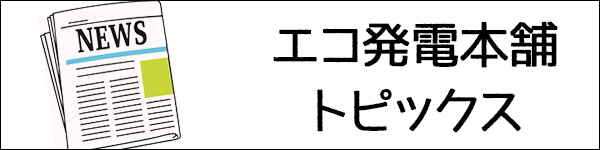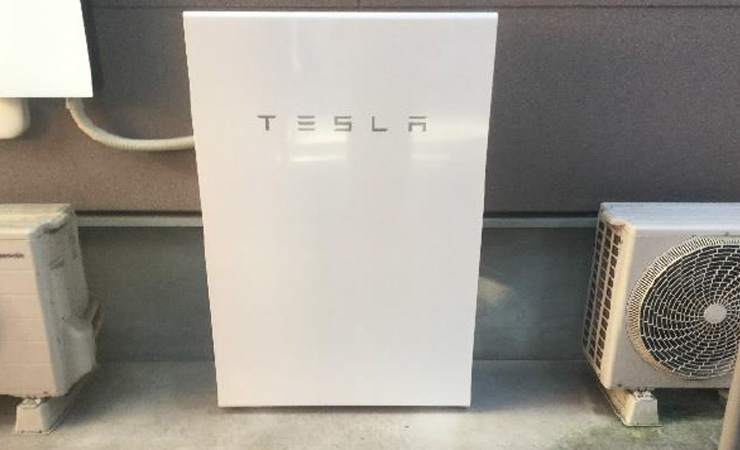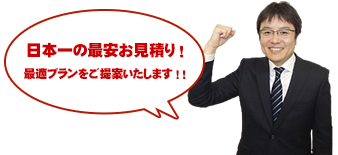エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
蓄電池の補助金とは
日本は台風や地震といった自然災害に見舞われる機会が多く、局所的あるいは広範囲にわたって停電が発生することもしばしばです。
災害時の停電は命に関わることもあるため、日本政府では環境保全目的の他にも、安全対策の一環として一般家庭や企業への蓄電池導入を推進しています。
しかし、蓄電池の導入には設備費や工事費など多額の初期費用が必要となるため、普及のハードルが高いという点がネックになっていました。
そこで、考案されたのが蓄電池の導入における経済的負担をサポートする補助金制度です。
補助金制度を上手に活用すれば、一般的な収支の家庭でも効果的に負担を軽減して蓄電池の導入を実現できます。
なお、蓄電池の補助金は「国が行っているもの」と「各自治体が行っているもの」の2種類があります。申請先や手続き方法がそれぞれ異なるので十分に注意しておきましょう。
申請を受け付けている期間は各補助金制度で統一されている訳ではありませんが、タイミングが合えば併用できるので経済的負担を大きく軽減することも可能です。
▶ 蓄電池の価格相場と補助金の詳細はこちら
▶ CEVのV2H補助金、EV補助金の詳細
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
蓄電池の国の補助金
国の補助金は、対象となる蓄電池や太陽光システムの導入を検討しているほぼすべての世帯に当てはまるため、毎年競争率が非常に高いです。
一方で、補助金の対象となる蓄電池は種類が限られており、補助金の条件に合致する蓄電池を選ぶこと、申請手続きを迅速に進めることが重要です。
また、給付される補助金の額は施工費用のほかに蓄電池の容量にも左右されますので、中途半端な容量の蓄電池を購入するよりは、必要を満たすに十分なものを選ぶのがおすすめです。
なお、補助金を計算する際は、蓄電容量ではなく初期実効容量を基準にして算定しますので注意しましょう。
補助金を受けられる条件としては、基準を満たし、SIIに事前登録された災害対応型の機器で、10kW未満の太陽光発電と併設可能な商品であること、新規に設置したもののみで中古やレンタルは対象外となること、設置費用が目標価格以下であることなどが挙げられます。
▶ 蓄電池の補助金の詳細はこちら
蓄電池の国の補助金の概要
国が行っている蓄電池に関する補助金制度は、国庫を財源としています。
補助金の内容や名称は基本的に1年前後のサイクルで切り替わるので、新しい情報をチェックし続けることが重要です。
2021年度の家庭用蓄電池設置における補助金は「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業(C事業)」という名前で実施されました。
「DER補助金」という俗称で呼ばれることもあるので覚えておきましょう。
予算は45.2億円で、補助の対象となったのは住宅用・業務用・産業用蓄電システムの新規設置者です。
また、国が実施している補助金は一般社団法人の「環境共創イニシアチブ(SII)」が受け付けています。
蓄電池の国の補助金額
補助金制度でどの程度負担を軽減できるのか、具体的な金額が気になる人も多いでしょう。
蓄電池の導入に際して国から補助してもらえる金額は、蓄電池の容量や契約内容などの条件によって変動します。
例えば、2021年度のDER補助金では「初期実効容量×4万円/kWh」という計算式で補助する金額を算出していました。
ただし、補助してもらえるのは蓄電池に関わる工事で発生した金額の3分の1が上限となっています。
また、DER補助金は「太陽光発電システム」「蓄電池」「HEMS」の3つが揃っている申請者を対象としていました。
HEMSは「ホームエネルギーマネジメントシステム」の略称であり、一般家庭で使用する電気エネルギーの把握と最適化を目的としたシステムです。DER補助金ではこのHEMSの設置工事に対しても補助金が出されていました。
補助上限は10万円ですが、工事に際して発生した費用の2分の1以内という条件付きです。
補助金はあくまで負担を軽減するための制度であり、工事費用の満額を支給してもらえるものではないので覚えておきましょう。
蓄電池の国の補助金の申請の流れ
蓄電池の補助金には複数の組織が関わってくるため、申請にはいくつかのステップがあります。
2021年のDER補助金は6月に申請の受け付けが開始されました。
まず補助金の対象となる条件を確認した上で申請を行ったら、交付が決定されるまでは待機となります。
一般的にはスムーズに手続きが進んだ場合で、申請から補助金の交付決定までは数週間の期間が必要です。
なお、手続きの関係上蓄電池の設置業者と契約を結ぶのは「補助金の交付が決定されてから」である点には十分注意しておきましょう。
見積りや相談を行う分には問題ありませんが、補助金の申請前や交付決定前に工事の請負契約を結ぶことはできません。
蓄電池の設置工事が完了したら電力会社の認定を受けて運転が完了となります。住宅環境や設置する機種にもよりますが、設置工事は数日から長くても1週間程度で終わるのが一般的です。
ちなみに、2021年度のDER補助金では年間1週間程度の実証事業への参加、それに付随した報告書の提出も必須となっていました。
蓄電池の国の補助金がもらえるタイミング
蓄電池の設置に係る補助金は、交付の決定が下りればすぐに受け取れるという訳ではありません。
まず、補助金の申請は受け付け先である環境共創イニシアチブが補助対象となる設備基準を満たしていることを確認した上で、随時交付の決定が行われています。
2021年度のDER補助金を例に取ってみると、公募期間は2021年4月9日~12月24日までに設定されていました。
交付決定の予定日は申請から約1~2週間後となっており、補助金の支払い期限は2022年3月31日まででした。
国からの補助金は比較的申請から交付決定までの期間が短い点が特徴ですが、それでもいつもらえるかが確約されているものではありません。
受け付け状況や審査の進み具合によって交付決定日が前後する可能性があるので留意しておきましょう。
蓄電池の国の補助金の注意点
蓄電池の補助金を確実に受け取るためには、注意しておきたいポイントがいくつかあります。
例えば、補助金制度にはクリアしなければならない条件が設けられているので、すべての要件を満たしているかどうかを申請前によくチェックすることが大切です。
特に設置を予定している蓄電池の機種や容量については注意しておきましょう。
また、補助金制度は予め予算が定められているため応募多数の場合は先着順となります。
予算の上限に達した時点で申請の受け付けは終了してしまうので注意が必要です。
実際、2021年度のDER補助金は6月の受け付け開始から2ヶ月余りで予算の上限に達しています。
申請期限まで余裕があるとしても、なるべく早めに申請を済ませておくのがおすすめです。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
国が実施している補助金の申請方法
設置場所に関係なく利用できるのが、国が実施している補助金制度です。
環境省や経済産業省が行っている事業で、災害などで停電した時にも必要な電力を供給できる性能を持った太陽光発電システムや蓄電池等の導入を目的としています。
設置する設備の種類や性能、工事費に応じて交付額は異なりますし、申請方法が複雑で予約申請、交付申請、実績報告と複数回の手続きが必要なため、あらかじめ申請の流れを確認しておいた方がスムーズに進められるでしょう。
以下に、国が実施している補助金の申請方法を手順ごとに紹介していきます。
蓄電池の補助金の予約申請
予約申請は、見積もりの段階で一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に対して行う手続きです。
この段階で設置場所に関連する発電所や蓄電システムの容量、太陽光発電等の接続機器について審査を行い、申請受付に進めるかどうかを判断します。
予約申請は契約や購入、設置を行う前に済ませなければならず、かつ期限内に完了しなければなりません。
この手続きでは、原則として3社以上の施工業者から相見積もりを取る必要があります。最終的にどの業者を選ぶのかは自由ですが、補助金は最安値の見積もりを基準にして算定されます。
ただし、設置予定の設備を取り扱っている業者が限られている、特注の仕様になっている、住宅と一体型になっているなどの特殊な事情がある場合には、申請時に理由書を提出すれば免除される可能性が高いです。
予約申請が認可されると予約決定通知書が発行されますが、決定日から90日間で有効期限が切れてしまうため、この期間内に次の交付申請に進まなければなりません。
電力会社との協議が長引くなど、期限内に交付申請に進めそうにない場合には、交付申請遅延届出書を提出しましょう。
蓄電池の補助金の交付申請
交付申請は予約決定日から90日以内、または当該年度の交付申請提出期限までに行わなければなりません。
予約決定通知書が発行されてから電力会社と電力負担金や工事費について協議をして契約を結び、SIIに対して交付申請をするという流れですので、早めに協議に取りかかる必要があります。
90日以内に契約に至る見込みがない場合は、交付申請遅延届け出書を提出することで期日は延長できますが、この場合も交付申請提出期限は変更になりませんので、年度末に申請を行うときは日程を確認しましょう。
交付申請を終えると、SII側で予約申請の内容通りに契約が進められているか審査が行われます。
認可が下りて補助金の交付対象となったら、交付決定通知書が発行されます。
この交付決定がなされてから蓄電池の発注をする必要があり、逆の手順では補助金交付の対象外となりますので注意が必要です。
蓄電池の補助金の実績報告
実績報告は、発注から電気工事及び設備の設置、引き渡し、支払いまでの内容を報告書にまとめて提出する手続きです。
これらの手続きを全て終えなければ補助金の交付が受けられませんので、期限内に必ず済ませておきましょう。
なお、ここまでの期間を補助事業期間といいますが、この期間内に発電システムから蓄電池に電力の供給が行われていなくても問題はありません。
しかし、少なくとも蓄電池に電源が入る状態になるまでは勧めておく必要があります。
また、実績報告の段階で費用の精算まで済ませておかなければならないため、支払いの証明には領収書の添付が義務付けられており、請求書で代用することはできません。
加えて、実績報告も期限が定められていますので注意しましょう。計画通りに全ての作業が終了したと判断されると認可が下り、補助金額の決定通知書の発行と共に補助金が給付されます。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
国の補助金を申請する際のポイント

国の補助金は競争率が高く、例年早期に受付が終了します。
そのため、確実に補助金が受けられるようにミスなしで申請を済ませることを心がけるのはもちろん、できるだけ短期間で手続きを終えるのが良いでしょう。
国の補助金申請をする際に注意すべき点を、以下に紹介します。
予算には限度があり先着順で受付が終了する
国の事業ということで期限ぎりぎりで申請しても問題ないと考えている人は多いですが、年度ごとの予算には限度があります。
そのため、先着順で申請を受け付けてはいるものの、補助金の交付額が予算の上限に達した時は期限の到来を待たずに予約の受付を終了します。
蓄電池は太陽光発電システムと並んで一般家庭の需要も高く、毎年補助金の申請件数も非常に多いです。
そのため、締め切り前に早期受付終了することがほとんどであり、購入や設置を検討する段階で準備をしておいた方が良いでしょう。
実際、翌年の2月を期限と設定していたにもかかわらず、その年の8~9月には受付を終了するというケースが見られます。
対策としては、蓄電池の設置を検討する段階になったら補助金の予算残高を確認し、早目に対処するというのが最善です。
予算残額はSIIのホームページで随時更新されていますので、こまめにチェックしておきましょう。
蓄電池は交付が決定してから購入する
交付申請手続きが複数回に渡る上、それぞれに期限が設けられていることを勘案して、早めに手続きを進めてしまおうという人も少なくありません。
しかし、補助金は申請すれば必ず給付されるというものではなく、審査を経て条件を満たしたものだけが交付を受けることができます。
交付決定前に契約や発注を行った蓄電池に関しては、経費が補助金の交付対象外となるため、正規の手続き通りに進めなければなりません。
以上の点から、契約や設置のタイミングは電力会社や施工業者とも十分協議した上で、交付が決定してから蓄電池を購入しましょう。
なお、手続きを迅速に進めるために正式な契約ではなく仮契約を業者と交わすこと自体は問題ありません。
交付が決定した後の購入を前提として、進められるところまで業者と話し合っておくのも良いでしょう。申請手続きを何度も行っている業者であれば、手順に従いながらスピーディーに手続きを進められるようにサポートしてくれます。
補助金の申請は個人では行えない
国の補助金を交付申請する場合は、蓄電池を購入する個人が手続きを行うことはできません。
補助金の交付対象に該当する蓄電池等の設備の導入や工事を行う業者が、事前にSIIに申請者代行登録を行うことで、手続きができるようになります。
逆に言えば、対象となる蓄電池を取り扱っている業者であれば、申請手続きの手順も把握しており、面倒な手続きを代行してもらえるので安心です。
代行手数料は別料金の場合と、施工費用に含まれている場合がありますので、見積もりできちんと確認しておきましょう。
国の補助金の交付申請は手順が複雑なこともあり、申請代行者がスケジュールを組んでその都度指示を出すのが一般的ですが、自分でも確実に補助金が支給されるように手続きを確認しておくことが大切です。
また、業者探しをする際に、これまでに交付申請手続きを多く行ってきたところを探せば、トラブルに巻き込まれる可能性も少なくなるでしょう。
補助金を受け取るまでには時間がかかる
蓄電池の設置の場合、先に設置工事を済ませて後からゆっくり補助金の交付申請をするという手順が踏めないため、設置や補助金の交付に時間がかかります。
SIIの混雑具合にもよりますが、一般的には申請してから交付されるまで3カ月程度が必要とされていますので、導入を決めたらすぐに施工業者に相談したほうが良いでしょう。
導入に関しても、申請から工事完了までが早くて2カ月程度、長ければ半年近くかかってしまうこともあります。
なお、蓄電池本体の設置や配線工事自体は、半日から1日もあれば完了するケースがほとんどです。
流れとしては、まず複数の業者からの見積もりを取り寄せて予約申請を行い、決定が出たら電力会社に契約の申し込みをして、工事費等を協議します。
契約を締結してから交付申請を行い、決定が出たら蓄電池の取り寄せ、現地調査、設置工事、引き渡しから支払いまでの手続きをして、最終的に実績報告をするという手順です。
この報告が認可されてようやく給付を受けることができますので、時間がかかることをあらかじめ覚悟しておきましょう。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
蓄電池の地方自治体の補助金
補助金の対象となる条件についても、地方自治体が独自に設定しているため、各自治体によって大きく異なります。
一般的に共通している条件としては、その自治体のエリア内に居住していること、税金の滞納をしていないことなどが求められます。
また、交付の対象となる蓄電池も決められていることが多く、容量や太陽光システムと連携が取れるかどうかが条件に挙げられていることもあるため、購入前にしっかり確認しておきましょう。
国の補助金と同様に、各自治体が定めている期間内に対象機器を設置すること、中古やレンタルではなく新品であることなども条件として挙げられることが多いです。
地方自治体の補助金を申請する場合には、まず自分が居住している自治体で設置予定の期間内に補助金の交付が行われているのかを確認し、該当するものがあれば条件を詳しく調べてから蓄電池を探すという流れになります。
▶ 蓄電池の自治体の補助金の詳細はこちら
蓄電池の補助金の対応機器
地方自治体が実施している蓄電池の補助金に申請する場合も、所定の条件をすべて満たしている必要があります。
条件の内容は各自治体が独自に設定しているため、国のそれと同じではないということには注意してください。
申請期間は1年前後のスパンで区切られている場合が多く、予算に達した時点で受け付け終了となる点については国の補助金と同様です。
なお、国の補助金制度は基本的に家庭用蓄電池を対象としたものですが、地方自治体では民間企業向けにも補助金を用意しているところもあります。
家庭用と間違えて申請すると、審査落ちの結果が返ってくるまでの時間をロスしてしまうので事前によく確認しておきましょう。
補助金の内容や条件は各自治体によって異なるので、詳細は住まいがある自治体の公式ホームページなどをチェックしてみてください。
自治体からの蓄電池の補助額
各自治体でも限られた予算の中で補助金制度を展開しているため、それぞれで補助してもらえる金額は異なります。
東京都が実施した2021年度の家庭用蓄電池に関する補助金では、補助率は機器費の2分の1としていました。
国が「機器費+工事費」を補助の対象としていたのに対して、東京都では機器費に絞っている点が特徴的です。
補助の上限は蓄電容量1kWhあたり7万円まで、一戸あたりで受け取れる上限金額は42万円でした。
制度全体で確保されていた予算は30億7440万円と、比較的大規模なものとなっています。
蓄電池の自治体からの補助金がもらえるタイミング
地方自治体からの補助金をいつもらえるのかについては、国の補助金と大きく事情が異なるので注意しておきたいところです。
まず前提として各自治体では限られた人員の中で補助金制度の手続きを進めているため、自治体ごとで審査・手続きの進行スピードがまちまちとなっているので留意しておきましょう。
東京都の場合は書類審査に加えて、必要があれば現地調査を行い制度適用の要件を満たしているかどうかを確認しています。
内容・条件を厳密に審査した後、問題がなければ助成金確定通知書が発行される流れです。
東京都の例では申請書を提出してから約1ヵ月半~2ヵ月程度で交付決定通知書が送付されていました。
交付が決定した後に申請者が設置業者との契約を行い、実際の運転で取得したデータを実績報告書として提出することが必要です。
東京都ではこの実績報告書を確認して、5~6ヵ月程度で助成金確定通知書を送付します。
確定通知が届いてから約3週間後に、指定した口座に助成金が支払われる仕組みです。このように、東京都の場合は早くても申請から受給まで7ヶ月程度かかります。
補助金を工事の前にもらうことは可能?
蓄電池の設置にかかる初期費用は小さいものではないため、できるだけ早く補助金を受け取りたいという人も多いでしょう。
実際の工事よりも前の段階で受け取れれば、家計への一時的な負担を軽減できます。
しかし、蓄電池に関わる補助金はその手続きの仕組みや制度趣旨の関係で、設備の設置・運転が完了した後の報告書が提出されて初めて支払いが確定するものです。
国・地方自治体の種類を問わず、蓄電池の補助金は工事より前に受け取ることはできないので覚えておきましょう。
▶ 蓄電池の価格相場
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
地方自治体が実施している補助金の申請方法
地方自治体が実施している蓄電池の補助金に関しては、自治体ごとに判断が異なるため、交付を受けるための条件や金額、必要書類、手続き等について統一された基準がありません。
また、補助金の交付自体を行っていない自治体もありますので、交付の有無や申請方法などについては自治体に問い合わせた方が良いでしょう。
地方自治体の補助金の場合、施工業者ではなく原則個人で申請しますので、施主にとっては国への申請よりも負担が大きいです。
ほとんどの自治体で蓄電池の設置工事を始める前に申請が必要ですが、郵送や窓口提出、オンライン申請などその手段も自治体によって異なります。また、国と同様に申請期限があるため、注意しなければなりません。
必要書類はだいたい国の補助金の交付申請と同じですので、施工業者に依頼しておけば揃えやすいです。工事前に必要書類を揃え、申請書を提出しましょう。
大体1週間~1カ月程度で審査が終了し、補助金の交付決定通知書等が発行されます。
これを受けて蓄電池の設置工事を行い、完了後に報告書を提出すれば補助金が支払われるという流れです。こちらも先着順で予算に達し次第受付終了となります。
地方自治体の補助金を申請する際のポイント
地方自治体の補助金は、国の場合と違って地域によってタイミングや条件等がそれぞれ異なります。
しかし、条件が合致すれば国の補助金よりも申請者の数が少ないため、気持ちにゆとりをもって申請することができます。
とは言え、開始時期や受付の期限も自治体によって異なるため、常に最新の情報を収集しておいた方が良いでしょう。
以下に、地方自治体の補助金を申請する際のポイントを紹介していきます。
◆ 国の補助金と併用することもできる!
一つの蓄電池設置工事に対し、国が管轄している複数の補助金を併用して受け取ることはできません。一方、地方自治体の補助金は時期や地域によって受けられないこともありますが、国の補助金と併用することが可能です。
もちろん、どちらかの補助金の受付が終了していても、一方がまだ申請可能であれば片方だけ交付申請をすることもできます。
双方から補助金を受け取ることができれば、従来の価格よりも大幅にお得な金額で蓄電池の設置ができますし、見積もりで条件の良い施工業者が見つけられれば、さらに満足度は高くなるでしょう。
国と地方自治体、両方に申請を出す場合には、それぞれの条件をよく確認して、どちらの条件も満たしている蓄電池を選ぶ必要があります。
また、申請や契約、施工のタイミングをよく確認してから作業を進めるようにしましょう。
◆ 補助金の申請は個人で行う
国の補助金は申請代行者しか行えませんが、地方自治体の場合は原則個人で交付申請を行います。
そのため、必要書類は自分で用意する必要がありますし、申請書の作成や必要書類の添付、スケジュール調整、自治体から交付される決定通知書の受け取りなどをすべて自分で管理しなければなりません。
手順が複雑で手続きが面倒、忙しくて申請ができないという場合には、費用はかかりますが申請代行を利用することも可能です。
元々国の補助金を申請する予定であればタイミングとしてはそれほど大きなずれが生じませんし、地域密着型の施工業者ならば、そのエリアの地方自治体の補助金交付申請についても詳しいため、安心して任せられます。
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
確実に補助金を受け取るために気を付けたいこと

蓄電池の設置費用が高額であるように、それを補助するための制度で受け取れる金額も少ないものではありません。
そのため、万が一補助金を受け取ることができなかった場合の負担は看過できないと言えるでしょう。
予期せぬとトラブルを防ぎ、確実に補助金を受け取るためには以下の点について十分注意して手続きを行ってください。
信頼できる業者を選ぶ
蓄電池の補助金を確実に受け取るためには、まず信頼できる販売店・設置業者を選ぶことが大切です。
蓄電池の仕様や機能については比較的難しい専門用語が用いられていることも多く、一般的な消費者がすべての項目を正確に把握するのは容易ではありません。
加えて、こうした専門用語は補助金制度の内容や条件についての説明にも登場するため、何も知らないままでは正確に手続きを進めることは難しいのです。
蓄電池の販売・設置を行っている正規の業者であればこうした専門用語や制度について正しい知識を身に付けているので、契約の際に相談しながら着実に手続きを進められます。
家庭用蓄電池事業はニーズが高まっていることから参入する業者も増えていますが、中には違法性が疑われる悪徳業者がいるのもまた事実です。
信頼できる業者を選ぶためには、販売・施工実績やアフターサービス・サポートが充実しているところに依頼するよう心がけましょう。
各業者の公式ホームページを参照するだけでなく、実際の利用者が投稿している口コミなども参考にしてみてください。
また、インターネット上では複数の業者に対して一括で見積り依頼を行えるサービスを展開しているサイトもあります。効率的に業者を比較することができるので上手に活用してみましょう。
蓄電池の補助金を申請することを業者に伝えておく
補助金制度を利用するつもりである旨を販売店・設置業者に伝えておくことも、確実に補助金を受け取るために重要なポイントです。
市販されている蓄電池の多くは補助金の対象であるものの、すべての機種が対象となっている訳ではありません。
補助金の金額も容量によって変動するため、正確な見積りを算出するためには業者の協力を得るのが近道です。
事前に補助金に関する情報を共有しておけば、支給の条件に当てはまっているかどうかを確認しやすくなります。
補助金に関しての知識や実績が豊富な業者であれば、対象となる機種・具体的な申請方法などについてアドバイスをもらえる可能性も高いです。
特に地方自治体の補助金制度については地域密着型の業者が強い傾向にあるので、不安点や疑問は積極的に相談してみてください。
指定された期間内に設置する
蓄電池の補助金は、蓄電池システムを設置するタイミングについても十分注意しておく事が必要です。
原則として蓄電池の補助金は「新規の設置」が条件となっています。
そのため、設備を設置した後に申請しても補助金を受け取る事は出来ません。
また、補助金制度は申請期間が設けられていますが、設備の設置についても期限が定められているという事も覚えておきましょう。
例え申請期限内に手続きを開始したとしても、設置期限が守られていなければ補助金は交付されません。
設置業者との契約は交付決定の通知が届いてからになるため、設備の設置期限から逆算して余裕を持って申請しましょう。
また、その際には審査に必要となる期間も考慮しておくようにしてください。特に地方自治体の補助金制度では審査時間が長めにかかる傾向があるので注意がしましょう。
蓄電池の補助金について期限が設けられているものとしては、もう1つ実績報告書というものが挙げられます。
すべての補助金で提出が求められる訳ではありませんが、多くの制度では必要となるので心得ておきましょう。
実績報告書は設備が実際に設置・稼働していることを証明するためのものであり、補助金の交付は多くの場合この報告書を提出した後に実施されます。
補助金制度の内容によってはさらに設備の写真を撮影して提出しなければならないケースもあるのです。こうした書類・証拠画像にも提出期限が設けられています。
また、申請期限・設置期限・書類等の提出期限はそれぞれバラバラに設定されている場合が多いです。
それぞれの期限をメモするなどして正確に把握して、実施漏れが無いようにスケジュールを管理してください。
早めに補助金を申請する
蓄電池の補助金制度は申請から実際の受給までにある程度のタイムラグが生じます。
手続きのスピードが早いと言われている国からの補助金でも、1ヶ月前後は見ておく必要があるでしょう。
設置業者の工事受け付け状況によっても受給までの期間は変動するため、なるべく早く受け取るためには、申請も早めに済ませておくのがポイントです。
また、一般家庭への蓄電池普及は年々注目度が高まっており、補助金制度の存在も広く認知されるようになりました。
それに伴って制度の利用を希望する人も増加傾向にあるため、申し込みが開始されても早々に予算上限に達してしまうケースは珍しくありません。
抽選ではなく先着順となっているので、確実に補助金を受け取るためにもスピーディーな意思決定を心がけましょう。
条件を満たしていても、申し込みが締め切られていては意味がありません。既にその年の補助金が締め切られてしまっている場合は、次年度の補助金についてこまめに情報をチェックし続けましょう。
▶ 蓄電池の業界最安価格の見積り依頼はこちら
エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」
| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |
|---|---|---|
|
ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |
V2H トライブリッド 給電器・充電器 |
長州産業 |
| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |
|---|---|---|
|
お見積り|太陽光 |
蓄電池の補助金に延長はあるの?制度の注意点について

蓄電池の補助金の概要を再確認
家庭用蓄電池に関する国からの補助金には2021年に実施されている「蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業費補助金」や2020年に募集された「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」などがあります。
どちらも蓄電池という名称が付いていて、補助金の対象として蓄電池が中心になっていることがよくわかるでしょう。
このような国の補助金制度は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が公募しています。
SIIは国からの補助金事業を受託して実施する役割を果たしている期間で、関連する企業が多数所属しています。
補助金制度は助成金制度とは異なり、制度の条件を満たす形で工事などを実施した場合に、費用の一部を補助金として支給してもらえる制度です。
条件を満たさない部分があった場合には適用されず、全額が支給されることも原則としてないので注意しましょう。
しかし、まとまった金額の補助を受けられることが多いため、蓄電池等の設置に際して負担が大きく軽減されます。
◆ 補助される金額
家庭用蓄電池の補助金制度は種類によって補助の金額に違いがあります。
SIIが実施している補助金制度ではどの程度の金額になっているのかを2020年に実施された例に基づいて確認してみましょう。
まず、家庭用蓄電池本体の設置については補助の金額は初期実効容量1kWhあたり2万円と定められていました。
蓄電池の定格容量に基づいて補助金額が決まるのではなく、初期実効容量に応じて決定されるのが注意点です。
SII補助金ではHEMS(ヘムス)についても補助の対象となっています。
HEMSがあると電化製品に接続することで電気やガスの使用状況をリアルタイムで確認したり、コントロールしたりすることが可能です。
HEMSへの補助金はシステム自体かかる費用の2分の1で、上限は5万円です。
蓄電池やHEMSの設置には工事が必要になりますが、SII補助金を使うと工事費についても補助をしてもらえます。
工事費に対する補助の金額は工事費用の2分の1で、上限は5万円です。
補助金の支給について2020年のときには予算を38.5億円としていました。
補助金を申請して家庭用蓄電池などを条件に該当する形で導入した人たちに支給していって予算に到達するか、募集期間が来たら補助金制度が終了する仕組みになっています。
◆ 補助金交付の目的
国が予算を立てて家庭用蓄電池を補助している目的は、直接的には蓄電池の普及です。エネルギー問題が世界的に取り組まなければならない課題となり、国としては企業だけでなく個人にも解決に向けて協力を要請しなければならない状況になっています。
蓄電池の導入は再生可能エネルギーの普及を促進するシステムを整えるのに使えるため、持続可能な社会を作り上げることにつながります。
国としては分散型エネルギーリソース(DER)の活用も促進する目的があり、安定して稼働する効率的な電力システムの構築を経てエネルギー問題の解決を進めることを目指しています。
そのため、国が主導している家庭用蓄電池の補助金制度では条件を厳しく設定して、要件を満たしている蓄電池の導入の際に補助金を出す仕組みになっています。
蓄電池の価格を下げて多くの人の手に届くようにする目的もあることから、設備費が目標価格を下回っていないと補助金を使って設置できないのも特徴です。
補助金交付の目的は制度の活用による家庭用蓄電池の設置の推進と、家庭用蓄電池の価格低減による普及率の向上という二面性があるのです。
◆ 蓄電池の補助金がもらえる条件は?
家庭用蓄電池の補助金制度で満たさなければならない条件がそれぞれ定められていて、毎回全く同じというわけではありません。
ただ、共通している条件もあるので確認しておきましょう。
まず、蓄電池を新規設置したときというのが補助の重要な条件です。住宅用、業務用、産業用の蓄電システムのどれを導入した場合でも問題ありません。
家庭用太陽光発電システムとよく言われている10kW未満の太陽光発電をこれから設置するか、すでに導入済みというのも条件です。再生可能エネルギーの利用を促進することや災害時の対応をできるようにすることを目的としているからです。
上述のように蓄電池の設備費が目標価格を下回ることが要件になっています。
導入する蓄電システムが補助金の受給対象製品として登録されていることも必要なので、大抵は蓄電池本体の価格については問題になることはありません。
この他にもメーカーによる無償保証期間とサイクル寿命が10年以上あることなど、いくつかの条件があります。すべての条件を満たしていることで補助金を手に入れられる仕組みなので注意しましょう。
▶ 蓄電池の補助金の詳細はこちら
◆ 補助金の申請期間について
家庭用蓄電池の補助金制度は申請期間内に書類を整えて申請しなければ利用できません。
これまでの補助金はどのようなスケジュールで募集されていたのでしょうか。
2020年度に実施された「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」では、2020年4月7日に開始されて2020年6月30日まで申請を受け付けていました。
その前年度にも同じ名称の補助金制度があって募集がおこなわれていましたが、公募期間は同じではありませんでした。
2019年度の補助金制度では一次公募が5月下旬から9月30日、二次公募が10月1日から11月29日というスケジュールで実施されていました。
さらに前年の2018年度は蓄電池単体を対象とする補助金制度は国によって実施されていませんでした。
このように家庭用蓄電池の申請期間は年度によって大きく異なります。家庭用蓄電池の補助金を利用するときにはスケジュールを確認してできるだけ早めに申請するのが賢明です。
▶ 蓄電池の補助金の詳細はこちら
家庭用蓄電池の補助金の申請に延長はある?
家庭用蓄電池の補助金はスケジュールが延長される可能性があるのでしょうか。
2020年度の「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」はもともと6月末時点で募集が終了するはずでしたが、8月末まで期間が延長されたという経緯があります。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で申請に時間がかかるケースがあることが考慮されました。
社会の情勢や予算の消化状況などに応じて申請期間が延長される可能性があることがわかります。
ただし、補助金制度は予算が定められているため、上限に達した場合には終了になります。
延長された場合でも予算がなくなり次第、募集が打ち切られるでしょう。
予算が減ってくるとSIIがホームページで告知しているので、状況を確認しながら申請の準備を整えるのが大切です。
補助金を受けるときに注意したいポイント!
家庭用蓄電池の補助金制度を利用すると購入や設置にかかる費用の負担が軽減されるのは魅力的です。しかし、家庭用蓄電池を手に入れるときに必ず補助金を利用できるとは限りません。
ここでは補助金制度を活用する際に注意しておいた方が良いポイントをわかりやすく紹介します。
制度の利用を検討するときには一通り理解してから準備に取り掛かりましょう。
◆ 支給条件をよく確認する
家庭用蓄電池の補助金制度は国や地方自治体が目的を持って進めている事業なので、補助をしたことによって目的が達成されなければなりません。
補助金の支給条件はいくつも設定されていて、同じ名称の補助金事業でも年度によって条件が異なる部分もあります。
一つでも条件を満たしていないことがわかったら支給されないので、蓄電池の設置や申請の準備を始める段階で支給条件を詳しく確認しましょう。
家庭用蓄電池の機器の種類や設備費、購入時期や契約時期などに加え、太陽光発電システムが既に設置されている必要があるかどうかを確認が必要です。
蓄電池の設置を依頼する業者にはどの補助金制度を利用したいかを伝えて、見積もりの時点で補助金の条件を満たす仕様になっているかどうかを細かくチェックしましょう。
書類上で条件を満たしていることが確認できないと補助対象にはならないので気を付けなければならないポイントです。
◆ 申請期限に注意する
補助金制度の申請期間についても注意が必要です。
あらかじめスケジュールされている期限があり、延長されない限りは申請期限に間に合わなかったときには補助金を利用できません。
日にちだけでなく時刻まで定められているのが一般的なので、日時を正確に把握して申請が遅れないようにしましょう。また、予算上限に達したときのように申請期限よりも早く終了することもあります。
国も地方自治体も予算を組んで運用していますが、緊急で他に予算を使う必要が生じた際などには打ち切りになる可能性もないわけではありません。
家庭用蓄電池は早く設置して運用してもらいたいため、基本的に募集は抽選ではなく先着順です。申請期限ぎりぎりでも大丈夫だと思わずに、できるだけ早く準備を整えて申請しましょう。
特に全国から利用できる国の補助金や、人口や住宅数が多い東京都の補助金は早期終了しやすい傾向があります。
◆ 必要書類をすべてそろえる
補助金の申請では必要書類がすべて整っていなければなりません。
制度によって必要書類には違いがありますが、申請書や提案書、見積書などの用意が必要です。
国の補助金では団体概要や直近の決算報告書、補助事業の要件及びその審査に関する説明書などの提出が求められています。
書類の不足や記入漏れなどがあると補助金事業として採択されず、支給されないリスクがあるので気を付けましょう。
書類は蓄電池の設置について相談している業者に代行して依頼してもらうのが安心です。補助金制度を利用して蓄電池を設置したいことを伝えれば対応してくれるので必要書類の提出は業者に任せましょう。
ほかにも使える補助金制度がある!
家庭用蓄電池の導入に使用することが可能な補助金制度は以上で紹介したものだけではありません。
正式名称にも略称にも蓄電池という名前が入っていない補助金制度でも、補助金の支給条件と家庭用蓄電池の設置の仕方によっては活用できる可能性あります。
ここでは家庭用蓄電池に利用できると考えられる代表的な補助金制度を紹介するので、条件に合うように設置できるかどうかを検討してみましょう。
◆ ZEH補助金
ZEH補助金はネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の推進を目的としている補助金で、一定の基準を満たすZEHに対して支給されるのが特徴です。
ZEHは生活によって使用される一次エネルギーの消費量を、再生可能エネルギーの発電システムの導入によってトータルでエネルギー収支をゼロにした住宅です。
建物の断熱性を高めたり、効率の高い設備システムを導入することで省エネルギーの実現と発電したエネルギーの有効活用を進めることでZEHを実現できます。
太陽光発電システムに蓄電池を付帯させて設置することも可能なので、ZEH補助金を活用することが可能です。
ただし、ZEH補助金の2021年度の公募は三次公募受付まで終了しています。今後も制度が継続される可能性が十分にあるので利用を検討してみましょう。
◆ VPP補助金
VPP補助金は分散型エネルギーリソース(DER)を構築し、バーチャルパワープラント(VPP、仮想発電所)を整備する実証を目的として出されている補助金です。
DERの補助金とも言われていて、VPPを作り上げるための基盤となるDERとして家庭や工場の蓄電池などの設置に補助が出る仕組みになっています。エネルギーリソースを増やし、遠隔で統合制御できるようにするVPPの実証実験に参加することが前提となる補助金制度です。
VPP補助金はVPP基盤整備事業やVPPアグリゲーター事業などに分かれていて、蓄電池が対象になっているVPPリソース導入促進事業は2021円1月18日の時点で交付申請の受付が終わってしまっています。
実証実験の進捗によっては再度募集がある可能性もあるのでVPP補助金の動向も確認しておくと良いでしょう。